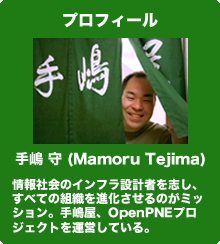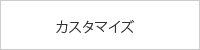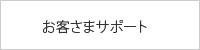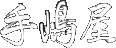社長BLOG
OpenPNE上に会社をつくる
- 2010-11-09 (火)
- 社長BLOG
通勤時間はもったいない。時間がかかるだけならまだしも、モチベーションを下げてしまう可能性まである。
もっと言えば、そもそも世界中の優秀な人達と一緒に仕事をするためには、通勤があってはならないのではないか。
OpenPNEで作られたサイト上に会社をつくることができれば、この課題をクリアできるのではないか。
オフィスに出勤せずに、ネット上のOpenPNEに出勤する。
オフィスや工場を会社と思わずに、OpenPNEが会社のイメージになる。
オフィスに託児所をつくるのではなく、託児所のそばで働く。
これをゴールに、OpenPNE上での会社作りにチャレンジする。
※連載になる、、、予定
「求める人同士を直接つなぐ」のがネット
- 2010-11-09 (火)
- 社長BLOG
東急ハンズで見て、企業の直販サイトで買う
本屋で立ち読みして、Amazonで買う
転職サイトで求人票を見て、企業の採用ページに直接申込む
これらすべては、ネットによって実現したことだ。
商品をつくる人とそれを手に入れたい人
希望の仕事につきたい人と、雇いたい人
ネットの本質のひとつは、
「求める人同士を直接つなぐ」
ことにある。ネットの登場によって、既存の企業はビジネスモデルの変更を迫られるかもしれない。
例えば、東急ハンズのような業態の場合
「お客からは入場料を取る。メーカーからは展示料を取る。」
この形態に移行し、ネット販売専門にしてもいいかも。
専修大学の講演で発見したこと
- 2010-11-04 (木)
- 社長BLOG
学生から質問をもらった。
yuz_mikan Nov 02, 5:46pm via yubitter
@tejima 絶対にソフトウェア化するべき・してはダメだと考えているものはありますか??
この質問。
OpenPNEによって社会をどんどんソフトウエア化していこうという話をしたことに対して、こんな質問が来た。
それに対する返答で発見した。
自販機や自動ドアが「ありがとうございました」「いらっしゃいませ」と電子音でいうのは、ソフトウエア化によるあきらかな失敗だ。しかし、これはソフトウエア化してみてはじめて失敗だったことがわかる。
社会をソフトウエア化するにしても、絶対にしてはならないものがあるはずだ。手嶋も全部何でもかんでもソフトウエア化すればいいとは思っていない。それでもまずソフトウエア化してみることで、これはやっぱり駄目だ、リアルのほうがいい。とはじめてはっきりわかるんだと思う。
※質問をしてくれてありがとう。
11/05 11/06 関西オープンフォーラムに参加
11月5日6日関西オープンフォーラムに参加する。
スケジュールは以下のとおり。
◆昼のスケジュール
5日 関西オープンフォーラム
6日 関西オープンフォーラム
7日 学生とMTG
◆夜のスケジュール
5日 PNEナイト@アルバーダ
6日 仲間と@アルバーダ
7日 19:00ごろ東京へ
※関西方面のOpenPNE仲間にはお話できるようにお声がけします。連絡もお待ちしています。
連絡は @tejima まで。
専修大学で講義
- 2010-11-02 (火)
- 社長BLOG
講義の音声ファイルと、スライドをアップする。
OpenPNEプロジェクト、手嶋屋インターン、手嶋荘入居、いずれもぜひよろしく!
※http://twitter.com/tejimaまで連絡ください。
http://dl.dropbox.com/u/151520/tmp/20101102senshu-u.ac.jp.mp3
http://dl.dropbox.com/u/151520/tmp/20101102senshu-u.ac.jp.ppt
【年齢について削除しました】社会や組織インフラを考えたいWEBエンジニアを募集
- 2010-10-27 (水)
- 社長BLOG
※【追記】年代を示して人物像を明らかにしたかったのですが、法律違反でした。年齢条項を削除しました。
ひと通りのPC、携帯のWEBサービス開発を経験してきた。最近はソーシャルゲームの仕事をよくやっている。これもいいんだけど、同じことの繰り返しになり飽きてきた。ゲームほど派手じゃなくても、もっと役立つ社会インフラをやりたい。
こんな方は、ぜひ手嶋屋に参加し一緒に働いてください。
なぜTSUTAYAと航空会社のポイントサービスがのし上がったのか?
- 2010-10-25 (月)
- 社長BLOG
答え
金銭価値を自ら創造できる、「うちでの小づち」を持っているから。
ポイントとは、商品を買ったりサービスを利用したりすると、主に支払った金額に応じてその企業が発行するポイントを付与され、次回のサービスに現金の代わりに利用できる仕組みのこと。
次回の利用時に現金を使わずに購入できるので、ポイントは突き詰めると未来に対する値引きである。
国内でポイントの強者といえば、TSUTAYAのポイントとJALやANAなどの航空会社のマイレージが有名だ。
このポイントサービスは、もはや自社のポイントサービスの枠を超えて、数百もの提携企業で流通する、企業が発行する一大独自通貨圏を形成している。
さて、なぜこの2つのポイントがのし上がることに成功したのか?
かたや400円のDVDレンタル対、かたや片道2万円の航空チケットだ。やっている仕事にもそれほど共通点が見受けられない。
だが、この2つのサービスには「そもそもサービスとして空席のものを、ポイントの交換価値として提供することができる」という共通点がある。
TSUTAYAにおいては、貸し出されていないDVD。航空会社においては空席の航空券だ。
これらは、たとえポイントの対価としてさし出しても、元々売れなかったものなので企業に取って大きな痛手にはならない。
それでも利用者からしてみれば、普段400円だして借りているDVDがおまけで付いてきたポイントで借りられるわけだし、普段2万円払っていた航空チケットをマイルで交換することができる。利用者にとっての価値は通常の現金と同じくらいに感じられる。
これが、ポイントサービスにおける「うちでの小づち」なのだ。
ポイントサービスでのし上がるには、このうちでの小づちの仕組みが必要だと思う。
※自分の直感で書いているので、ひょっとすると間違っているかも知れません。あしからず。
プログラムでは時には設計をあきらめることも必要
- 2010-10-24 (日)
- 社長BLOG
プログラムの設計は、コンピューター上の世界や空間をデザインするというとてもクリエイティブな作業だ。
コンピューター上には制約やルールが少ないので、何パターンでも設計をすることができる。
これが良くもあり、悪く転ぶこともある。たいていはつくって、使っていくうちに当初の設計の不具合に気付き、設計を途中でどんどん変えていく。改善できればそれはそれでいいのだが、中には袋小路にはまってしまって、リカバリーがうまく行かないこともある。
自分の経験では、JavaMailにかなり苦労させられた。
OpenPNEの前身はPNEという転送メールのサービスで、当時学生だった自分はこの転送メールの処理をJavaMailでやろうと考えていたのだ。
JavaMailというのはJava上でメールを扱うためのライブラリなのだが、結論からいうと、この設計にかなり無理があった。
それまでJavaの設計は魔法使いのような人たちがやっているので、完璧なんだろうと思っていたが、そうじゃないこともあるんだとそのとき初めて感じた。
設計の対象である電子メールというものは、とにかく仕様がぐちゃぐちゃで、エレガントに扱おうとしても元々無理がある。ぐちゃぐちゃならぐちゃぐちゃのまま簡単に扱えるようにすればよかったのだが、それをがんばってJavaですべて設計してしまったところが、失敗だったと思う。結果として、メール処理関連だけで130個もクラスを作ってしまった。そもそものメールが複雑なので仕方ないにせよ、これはきつい。
どうすればよかったかというと、これといった結論は無いのだが、おそらくは、メール処理のコア部分にJavaを使わずに、Unixのネイティブプログラムやスクリプト言語などで、場当たり的なコードを書くべきだったと思う。
エクセルもゼロを発明すべきだ
- 2010-10-19 (火)
- 社長BLOG
エクセルの行は1から始まる。
これが非常に使いにくい。
たいてい一行目は見出しとして使うので、うまく並べようとしてもずれてしまうのだ。

そのため、番号の行を別に用意せねばならず、また頭の中で+1したり-1したり考えなければならない。
もしエクセルの行が0から始まれば、何件のミスが無くなるだろう。
IT土方という言葉について
- 2010-10-19 (火)
- 社長BLOG
IT土方、デジタル土方という言葉がある。
でも、土方からクリエイター、アーティストまでが地続きにつながっている業界って、そんなに多くないと思う。
そう考えると悲観することじゃない。
問題は、土方から卒業しようとしないこと。
そこにパソコンがあるのに、クリエイターになろうとしないことだと思う。