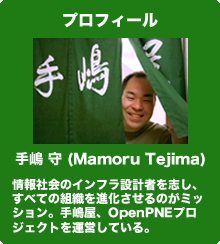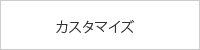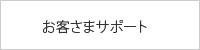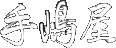社長BLOG
【結果報告】2/7 ノマドワークスタイル勉強会@表参道
休日の趣味として、ノマドワークスタイル勉強会を開催した。
コバヤシさん、ヤノさん、ナベタさん、イシオカさん、カゲヤマさんと自分の6人が参加。
場所は「パンとエスプレッソと」に集合。
http://allabout.co.jp/gourmet/bread/closeup/CU20090520A/
人数が増え6人となり、会場を急遽となりのトルコ料理屋さんに移動。
となりには、はらロールというロールケーキやさんができていた。
たくさん話したので、まとめるのが大変なので、箇条書きに。
・「仕事をするのにオフィスはいらない」に共感する人多いよね。
・固定的なオフィスが無いというのは、昔はかっこ悪かったよね。
・最近は「場所に縛られないカッコいい生き方をしている」という見方も出来るようになったよね。
・iPhoneやイーモバイル、クラウドなどのテクノロジー環境が発達したよね。
・仕事に向くゆったりとしたカフェも増えているよね。儲かっているかどうかはわからないけど。
・でも、ずっとスタバやルノアールって言うわけにも行かないよね。ちょっとしたミーティングはやっぱりしたいし。
・ある程度長時間働いていても後ろめたくない場所、というのもポイント高いかも。
・静かなら良いって訳じゃない。サードプレイスとしては、マックのようなごちゃごちゃしているところの方がはかどる場合もある。
・ノマドワーカーが一番必要としているのは、ネット環境ではなく電気じゃない?
・1時間分の電気を300円で販売する電気供給ポット型デバイス「電気ポット」があると良くない?
・不動産というのは、駅に近ければ近いほど高いのが普通だが、その見方が変わってきている。
・シェアハウスの場合、駅に近すぎると利便性を求めた人が集まるため、コミュニティが形成されない事がある。
・駅に近すぎるカフェなんて、同じようにあてはまるんじゃない?
・この会を単なる勉強だけに終わらせたくない。研究し、実際に実行する。実行委員会、制作委員会を目指したいな。
・まずは毎月勉強会を開催したい。次回は3月上旬。※仮で3/7とした。
・この会をビジネスで考えるよりも、ノマドワークスタイルに共同コミュニティ的な回し方のほうが適しているかもしれない。
・手嶋はノマドワーカーのゆるいつながり、コミュニティを管理する仕組みをOpenPNEで提供するよ。
※このテーマに興味のある方は、次回の勉強会に是非ともご参加ください。
iPadはジョブズの老眼対策のために作られた
- 2010-02-05 (金)
- 社長BLOG
「iPadはジョブズの老眼対策のために作られた」
twitterで発言したらかなりの反響有り。
これはずーっと考えていたこと。
2007年iPhoneを発表したとき、ジョブズはメガネをかけたりはずしたりしながらプレゼンテーションをしていた。
そのとき、ジョブズもずいぶん歳をとったもんだなー。と感じた。
ジョブズはいらいらしているに違いない。
まだ、自分はiPadは手に取っていないけど、多分老眼鏡をかけなくても使えるようにデザインされているんじゃないかな?
こんな期待をしている。
老眼対策機能付きのiPadなので、発売されたらうちの母親用に、すぐに買うつもり。
入念な初期設定として3ヶ月ぐらいは自分で使ってみるんだけど。
「さとり世代」の日本の勝ちパターン
- 2010-02-05 (金)
- 社長BLOG
「さとり世代」についてのブログ、色々反響をいただいた。
バブルだったり、団塊なオトナから見れば、さとり世代は活力が無く、消費せず、経済成長が止まってしまうのではないか?と言う懸念を持つかもしれない。
自分は、さとり世代な人たちでも、幸せな日本を作る方法はあると思っている。
それはわりと簡単で
「エネルギーや贅沢品など、なるべく無駄づかいをせず、世界中で売れるもの作って輸出する」
もっとかみ砕くと、
「引きこもって省エネ生活を送りながら、サービスを提供する」
となるかな?
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0603/20/news013.html
家入さんなんかは、モデルになるかもしれない。
だいたい形は変われど節約しながら外貨を稼ぐというのは、明治時代、もしくは戦後すぐぐらいの日本の姿なんじゃないか。
日本の将来はまちがいなく明るい。背伸びをせず、日本人の本来の感覚を持った人たちが増えていると思う。
日本人の感覚というとじゃあそれはいつの日本人だ?と言われるだろう。
江戸時代か?明治時代か?戦後か?なんて。
自分が思う日本人というのは、縄文時代から現在までの日本人の平均をとって表現するような物かな?
自分は日本人だし、日本人は世界一だと思っているよ。
自分が、オトナに頼みたい最後の仕事は、次世代のインフラも、産業保護もいらないから、借金をすこしでも減らして、そして早々に退場してもらうこと。
この少子化の時代、民主的にまともに選挙しても勝てないわけで、しかも若い連中を選挙に行かないようにし向けたのもオトナのしわざ。この尻ぬぐいは、やはりオトナがきっちりとけじめをつけるべきだ。
※オトナオトナと言ってはいるけど、自分も30才になって、十分おっさんの域にさしかかっているんだけどね。
「さとり世代」は名言だ
- 2010-02-03 (水)
- 社長BLOG
ねとらぼ:ゆとりの次は「さとり世代」? – ITmedia News
元ソースは2chなのだが、言葉がおもしろかった。
ゆとり世代の進化系はさとり世代とのこと。
「車に乗らない。ブランド服も欲しくない。スポーツをしない。酒を飲まない。旅行をしない。恋愛に淡泊。貯金だけが増えていく」「現代の若者が目指すのは、実にまったりとした、穏やかな暮らしである」など若者の消費傾向を紹介。これが日本経済にとってプラスかマイナスかを問いかける内容になっている。
この記事中にあるように、無理した消費をせずにまったりと穏やかに暮らしていくスタイルのことらしい。
そういえば、うちにいる学生でも
「最近バス良く乗るんですよ。安いし便利ですよ」
なんて話を聞いて衝撃を受けた。
学生で免許を持っている割合もどんどん減ってきている。自分たちの世代では、まだオートマにするかマニュアルにするか?と言う選択があるぐらいで、男はみんな免許を取っていた。
自分はこの「さとり世代」の動きは悪いことではなく、進化した日本人の登場であると思っている。
見栄を張って無駄な消費をするバブル世代の方が、よっぽど子供であり、世の中のためにもならない。
そんなバカがたくさんいるから、エコポイントやエコカー減税なんて、これっぽっちもエコでない、エコの名を借りた景気刺激の制度を作ってしまうのだ。
「さとり世代」はこの欺瞞を見抜いている。
彼らは、テレビを観ず、車に乗らないという、究極的な方法で、この欺瞞に反発をしている。
※なぜかパソコン用液晶ディスプレイはエコポイントがつかないのだ。これじゃ地デジという失敗政策の穴を埋めるために、消費をコントロールしようとまでしてるんじゃないかなんて、邪推しちゃうよね。
OpenPNEホスティングのフィードバックをください
- 2010-02-02 (火)
- 未分類
OpenPNEホスティング用フィードバックフォーラムを作成
- 2010-02-01 (月)
- 未分類
http://bit.ly/aJLB2U
So-netSNS終了に伴い、今後どうするか?を考えるフィードバックフォーラムを作りました。
So-netからスムーズに移行できる、
「OpenPNEホスティング」を開始するにはどうしたらよいか?
というのがテーマの中心になるとおもいます。
6月にSo-netSNS終了。サポート手段を提供する。
- 2010-02-01 (月)
- 社長BLOG
2006年6月から関わってきたSo-netSNSが、スタートから丸4年の今年6月で終了する。
大型SNSだけではない、マルチSNSの時代を二人三脚で作り上げてきただけに、サービスの終了はとても寂しい。
多くのオンラインゲームSNSをはじめとして戦場の絆や、ネオロマンスなど素敵なSNSが数多くあるだけに、出来るだけスムーズに移転できるように手を尽くしたい。
サービスの詳細はまだ決まっていないが、閉鎖の前5月中に、無料もしくは低価格のホスティングサービスを提供したい。
詳細はこのブログでお知らせする。
このSo-netSNSの関連タグはこちら。
https://www.tejimaya.com/tag/so-netsns/
※移転=>サポートという表現に変更。データを抜き出すのは規約上出来ないと思うので。
はまったレポート:OpenPNE3プラグイン公開の手続き
- 2010-01-30 (土)
- 社長BLOG
いやーはまった。
OpenPNE3のプラグインを公開するための手順が。
結局はうちの山田さんの技術メモで解決したのだけど、忘れないように改めてメモをしておく。
http://webmemo.uzuralife.com/article/1836
0.アカウント下準備
Redmineのアカウントとプラグインチャンネルサーバのアカウント。ふたつとも必要だそうだ。自分はすでに出来てるので、パス。ここは調うずら技術メモなどで調べてほしい。
1.Redmineにプロジェクト登録
Redmineはいろんなところからプロジェクトが登録できるようだけど、変な親プロジェクトにぶら下がってしまう可能性があるので、やたらなボタンを押さずに、このリンクから登録する。
http://redmine.openpne.jp/pear_package/add?project_id=op3-plugins
このように登録したあと、何も言ってくれないから悩ましい。
OpenPNEのプロジェクトサイトに表示したい場合には
http://p.pne.jp/d/201002012337.jpg
こちらのリンクからもプロジェクトの登録を行う。
うまくいくと、このページに図のようにリストされる。
http://redmine.openpne.jp/projects/op3-plugins

2.plugins.openpne.jpへの反映
同時に、プラグイン管理ページにも反映されるとのこと。
http://plugins.openpne.jp/4CYoEjm1PXzaTv.php
自分の場合はこのようになった。
英語か日本語か?メンテナのところにちゃんと自分が入っているかどうか?このあたりを確認してほしい。
3.プラグインパッケージの作成
今度は開発サーバに戻って、パッケージを作成する作業になる。
自分の場合は
./symfony opPlugin:release opLinkFriendPlugin ~/
ホームディレクトリに opLinkFriendPlugin-0.1.0.tgz ができあがる。
4.パッケージのアップロード
ここからパッケージをアップロード。
アップされると
このようにぺろっと表示される。
これはかなりレベルが高い。
5.動作確認
最後はOpenPNEをまっさらでインストールし、
symfony opPlugin:install -s beta opLinkFriendPlugin
とすれば、動作完了。なかなか大変だった。
メンバー全員とフレンドになる opAutoFriendPlugin
- 2010-01-30 (土)
- 社長BLOG
※opLinkFriendPluginはopAutoFriendPluginに改名しました。
会社の社員同士や、サークルの仲間同士など、すでに人間関係が出来ている組織では、わざわざフレンドリンクをするのは非常に面倒だ。
そんな組織のために、自動的にメンバー全員とフレンドリンクになるプラグインを作ってみた。
その名も opAutoFriendPlugin
使い方はREADMEを参照していただきたい。
https://github.com/tejima/opAutoFriendPlugin
CRONTABなどで一定時間ごとに起動するようにしておけば、
全員が自動的にフレンド関係になる。
OSSAJ フォーラム 2010 2月16日 15:20~18:30
- 2010-01-29 (金)
- イベント
OSSAJ主催のフォーラムで講演します。
内容はこちら。
15:20-16:00 講演3 「オープンソースプロジェクトを立ち上げ事業に活かそう」
~OpenPNEプロジェクトの事例から学ぶ~
講師:株式会社手嶋屋 代表取締役 手嶋 守氏
オープンソースは楽しいです、役に立ちます、儲かります。オープンソースは利用するだけではなく、プ
ロジェクトを立ち上げ運営することでその真価が発揮されます。手嶋屋はこれまで5年間、OpenPNEの
開発を通じてオープンソースプロジェクトに取り組んできました。そのおかげで国内のSI事業が年々縮
小する一方で、ソーシャルコンピューティングの世界において、独自のポジションを獲得することができま
した。本講演ではOpenPNEプロジェクトの事例を元に、オープンソースプロジェクト運営のアドバイスを
行います。
16:00-16:10 休憩
16:10-17:30 パネル・ディスカッション
パネリスト:上記講演者の方々と湯澤 一比古氏(OSSAJ会員)
司会:林 香氏(OSSAJ理事)
申し込みはPDFをダウンロードの上、メール送付してください。
http://www.ossaj.org/seminar/100216/ossaj_seminar_20100216.pdf