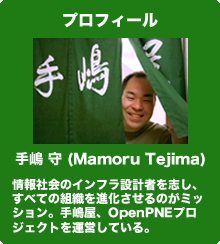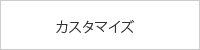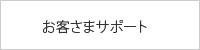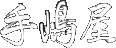社長BLOG
エンタメ=>ビジネス
- 2011-07-14 (木)
- 社長BLOG
今の流れは、エンタメ=>ビジネスだ。
Gmailはコンシューマーから始まった。ソーシャル・ネットワークも今の形のものはエンタメ由来である。
これが便利だから、会社でも、学校でも使おう。という話になっている。
昔は逆だった。
そこで考えたのが二本の企画。
◆ランチランダマイザー
会社向け。ルーレットでランチのメンバーが決まる
◆社員時計
会社向け。美人時計のコピー。社員が一分ごとにスイッチして時間を知らせてくれる。

ふざけているけど、これで会社組織はもっと良くなると思うんだ。
既存サービスを立体化させる
- 2011-07-13 (水)
- 社長BLOG

いつもソーシャル・ネットワークを研究しているとき、
ネットワークだ、ネットワークだといって、ついついつながりや情報の流通と伝搬ばかりに気を取られていた。
OpenPNEは既存サービスに、人やグループという概念を追加することができるというのも、大きな価値である。
これを、既存サービスの立体化と呼ぶことにする。
X軸は:自分に関する情報や機能
Y軸は:相手に関する情報や機能
Z軸は:グループに関する情報や機能
だ。従来のサービスはこの区別が明確でなかった。
既存サービスが使いづらく、ソーシャルサイトが使いやすい理由は、
この3つの概念が、人に取って分かりやすいということなんだと思う。
だから、既存サービスを立体化することで、もっと便利にすることができるようになるはずだ。
◆メーリングリストの場合
たとえばOpenPNEでメーリングリストを立体化してみよう。
◆自分のページ
X軸には、自分に関する情報と機能が並ぶはずだ。

・投稿したい
・最新の未読投稿、自分の発言を閲覧したい
・過去記事を検索したい
などが、自分がアクセスしたい情報であり機能となる。
◆相手のページ
Y軸には、MLに参加する別のメンバーの情報を配置する。

そのメンバーの情報を確認する。
そのメンバーにプライベートなメッセージを送る。
そのメンバーの過去の投稿内容を閲覧する。
◆グループのページ
Z軸にはグループの情報が配置される。
MLであれば、MLの参加、退会、メンバーのリスト、過去ログなどが表示される。

こういうように、OpenPNEを導入して情報を整理し、立体的に再配置することで、
従来のMLシステムより、直感的で分かりやすくなるとおもうんだ。
さらに注目したいのは、この3つの軸を表現する画面がほぼ同一のレイアウトで実現されているところだ。

これは2005年にmixiの初期レイアウトを研究した図。
初期のmixiは3つの主要画面のレイアウトが統一されていて、構造的に素晴らしかった。複雑な機能群をシンプルに見せることに貢献した。
OpenPNEと外部との連携ポイント
- 2011-07-11 (月)
- 社長BLOG

OpenPNEがプラットフォームとして外部と連携すべきポイントは、次の3つ。
◆ID連携
OpenPNEは、ネットワーク(組織やコミュニティ)をネット上に転写するものである。よって既存のネットワークのIDを表現するシステムと連携する必要がある。
いまOpenPNEでデフォルトで提供しているメールアドレスによる認証も、つきつめて考えてみればこの”ID連携”だといえる。
メールアドレスシステムという既存システムにID連携して、OpenPNEを使えるようにする。
ということ。
他にもOpenIDや各種の外部ソーシャル・ネットワークとシングルサインオンもこの範疇に含まれる。
◆プロフィール連携
OpenPNEは、個人の人となり、属性情報をネット上に転写するものである。よって既存のシステムが持つ、プロフィール=属性情報と連携する必要がある。
企業や学校の所属状況を、プロフィール、フレンド、コミュニティといったSNSの各種概念にマッピングしていく。
◆データ連携
OpenPNEは、ネットワークの活動をネット上に転写するものである。よって既存システムが持つデータやイベント情報を、OpenPNE上で表現する必要がある。
「メールが届いた」「来週末イベントがある」「自分の部署に新しい仲間が参加した」「ゲームでレベルが上がった」
などなど、組織上で起こったあらゆる活動記録は、OpenPNEを通じてソーシャル・ネットワーク内で共有される必要がある。
OpenPNE関連のブログフィード
- 2011-07-11 (月)
- 社長BLOG
OpenPNEにはいろんな人が関わっている。
自分もそうだが、OpenPNEに関連しないブログも書いたりしている。
OpenPNEの記事だけを複数のブログから集めたフィードを作ってみた。
RSSはこちら。YahooPipesで作っている。
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=ade105c50c02f163a97c5e1acc686ac6&_render=rss
このレシピは超簡単で、OpenPNEに該当しそうなブログRSSをマージし、時系列でソートするだけ。
少し工夫しているのは、”OpenPNE”とキーワードが入っている物だけを引っ張っている。

できあがりのRSSのサンプルはこちら。
「ここにもOpenPNE関連情報あるよ!」というブログはぜひ紹介いただきたい。
このフィードは、公式サイトにも掲載したい。
Google+の2の矢はGoogleApps対応だ
- 2011-07-08 (金)
- 社長BLOG

Google+はこのまま行けば確実に失速する。
Google+が放つ第二の矢はなんであろうか?
おそらく、独自ドメインのGoogleApps対応だろう。
そもそもGoogle+はこのために作られたんじゃないだろうか?
Google+はFacebookではなくて、実は対Chatterのサービスなのだ。
※そうでも思わないと、イロケがなさすぎて使ってられない。
なんでもクラウドにしてしまえ
- 2011-07-07 (木)
- 社長BLOG

かなり妄想が入っているので、話1/10くらいで。
感覚的に、Twitterが入ってきてから、相対的にフレンドとコミュニティの意味合いが薄くなった気がする。
しかも、Googleがサークルなんて、始めたりして、ソーシャルグラフの考え方が、さらにわからなくなってきた。
フレンドも、コミュニティもフォローも統合する概念が作れないかなと、ずっと考えている。
その一案が”クラウド”。
まあ、クラウドの名称は、いまどきキャッチーだよねってぐらいで、
この際グループでも、タグでも、クラスタでもいいのだけど。
「人を包みこむ輪っか」を表現する統合的な仕組みをつくりたい。
コミュニティは、”福島県出身コミュニティクラウド”
フレンドは、”手嶋のフレンドクラウド”
フォローは、”手嶋がフォロークラウド”、”手嶋をフォロークラウド”
サークルは、”手嶋の知人サークルクラウド”
ほら何とかなりそうだ(見た目だけなら)。
今OpenPNEに備わっているフレンドやコミュニティ所属モデルを統合すると、主に速度面がネックになりそうだ。
それでも他方で、概念がまとまっていたほうがチューニングの効果も一気にでるので、なんとかなるんじゃないかと思っている。
人を包み込む輪っかという考え方は、ソーシャル・ネットワークそのものであるので、概念としては長生きするはずだ。
Google+にダメだしその2 サークルに対称性が無いのは最悪
- 2011-06-30 (木)
- 社長BLOG
※2011/07/07追記 ザッカーバーグが全く同じことを言っている
公開範囲を指定する際に大事なのは、コンテンツ公開範囲の対称性、フェアであることだ。
Google+ ではデフォルトで”友だち”、”親戚”などのサークルが提供されている。
ここで?と思った。”手嶋守の友だち”ではなく、単なる”友だち”なのだ。
これは、同一名称のサークルが複数存在することを示している。
これは絶対にうまくいかない。
細かい説明はの話は飛ぶが要は、
情報の公開範囲に対称性がないのだ。
情報の送り手と受け手が、公開範囲を共有していない。
たとえば、自分が ”城北高校アメフトサークル” なんてサークルを作って、メンバーを入れても、
他のメンバーからはこのサークルに入っていることが感知できない。
他のメンバーが作った”城北高校アメフトサークル”は別のメンバー構成をしているのだ。
これはおかしい。
我々がサークルに持つ印象とだいぶ異なる。
Twitterの非公開リストと同じような考えであろうか?
※そうそう、話は全然違うけど、タイムラインは四角い印象で、サークルは丸い印象がある。タイムライン重視のサービスなら、サークルよりも、リストの方が表現があっている気がするな。
Google+に1点だけダメ出し
- 2011-06-30 (木)
- 社長BLOG
Google+は情報の公開範囲を細かく指定できる。サークル単位で公開できる。
Facebookは情報が公開されすぎてしまうので、この不具合を解消したかったのだろう。
人は情報のみをコントロールしたいのにあらず、人格もコントロールしたいのだ。
公開範囲を指定するのであれば、人格(ペルソナ)も公開範囲ごとに指定できなければならない。
人格はひとつのくせして、こいつ自分に隠してしゃべっていることがある。
と周りから思われるので、マイナスだ。
Facebookのように、人格はひとつ、ひとつの人格で包み隠さず全部共有せよ!の方が気持ちがいい。
※そのほうがOpenPNEの良さも引き立つしね
先端を進むこと、しんがりを引き受けること
- 2011-06-30 (木)
- 社長BLOG
コミュニケーション環境に対する絶対的な不満。
先進的なツールは、いろんなところがどんどんチャレンジをする。
結果としてコミュニケーション環境を分散させ、全体として使いにくくする。
どういう事か?
まず昔話から
Niftyのフォーラム時代は簡単であった。世界はフォーラムの中に閉じていて、この中に全員いるので、簡単だった。
電子メールの時代は簡単であった。全員に電子メールで連絡すれば良い。複数人に送りたければCCをしたり、メーリングリストを使ったりすればよかった。
mixiの時代は簡単であった。日本のネット住人はすべてmixiにいて毎日ログインしていたので、ここでメッセージを送れば、ここでイベントを企画すれば、全員に連絡が取れた。
今、どうだろうか?
日本国内では、まず3つのSNSがある。グローバルのSNSではTwitterとFacebookが上陸した。
Googleも性懲りもなくまた取り組むらしい。
SNSだけで6つ。それぞれあっちが好きだこっちが好きだと言っている人たちがいるので、
みんながどこにいるかがわからない。
結果、どの手段で連絡をとればいいのか、分からなくなってしまうのだ。
先端ツールの悪いところは、他のツールをきっちり殺さないところだ。先端ツール同士の戦いに忙しいので、古いツールはほっておく。
MLにトドメを、電話にトドメを、チャットにトドメを。
一つ一つのレガシーなツールに対し、完全置き換え可能なようにして、トドメを刺していくという活動も重要なのではないか?
新しいツールが増えるのに並行して、コミュニケーションの手段を減らしていかないと、理想とする状況にはならないんじゃないだろうか?
現に今、自分は困っている。
bit.lyのカスタムドメインモードを試してみるx.pne.jp
- 2011-06-28 (火)
- 社長BLOG
bit.lyは大変便利なサービスだが、最近だと長いものだと6文字ぐらい、どんどん長くなってきた。
これを案じたのか、bit.lyは各自が所有するカスタムドメインで、短縮URLを作れるようなサービスを無料で提供している。
早速試してみた。手嶋屋が持っているドメインで一番短いのは、pne.jp。これをそのまま使うわけには行かないので、
x.pne.jpで登録した。
いろいろ設定するとこのようになる。

http://www.teijmaya.com は無事に http://x.pne.jp/CVE2S このURLに短縮できた。
ふと確認してみようと思い、x.pne.jpの部分をbit.lyに変えてみたら、、、http://bit.ly/CVE2S
なんと同じサイトにアクセスした。。
なんだ、カスタムドメインといったからって、短縮URLまでカスタムになるわけじゃないのか、、、、、、。
カスタムドメインで短縮したら、文字列が短くなるのではと期待したので、
少しがっかりだ。