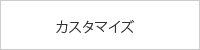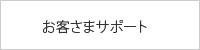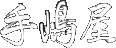社長BLOG
OA2.0 – オフィス(オーガニゼーション)オートメーション 2.0
- 2009-04-13 (月)
- 社長BLOG
OA機器のOAは「オフィスオートメーション」の略で、会社組織が紙と手作業で行っていた業務を電子化し、定型作業を自動化しようというもの。
どうも、自分が物心つくまえからあった言葉らしい。
OA2.0はOpenPNE上で組織のコミュニケーションや業務を行うことで、組織運営を電子化、自動化しようという試み。
OpenPNEは人と組織を表現し、WEB上でその活動を行えるようにするためのソフトウエアである。
OpenPNEで、OAという言葉を再定義したい。
digsbyのFaviconの使い方がカッコいい
- 2009-04-08 (水)
- 社長BLOG
digsbyはいろんなWEBサービスの新着情報をお知らせしてくれる常駐アプリ。
Gmailの新着メールをお知らせしてくれるのだが、Faviconの使い方がカッコいい。送られてきたFromのメールアドレスのドメインからFaviconを取得するのだ。
1.tejima@tejimaya.comからメールが届く
2.http://tejimaya.com/にアクセスしてFaviconを探す
3.見つけてきたFaviconをお知らせ欄で写真のように表示する
よくできてる。
既存メディアがソーシャルメディアを立ち上げるときによくする失敗
- 2009-04-08 (水)
- 社長BLOG
ソーシャルメディア事業者は原則的にコンテンツを作ってはいけない。
でも既存メディアはコンテンツを作って流すことに慣れているので、ついつい自前で(または買ってきて)コンテンツを消費者に提供してしまうのだ。これが既存メディア事業者が引き起こす主な失敗の原因だ。
「一方の消費者が作ったコンテンツをもう一方の消費者が楽しむ」という構図を作ることが、ソーシャルメディア事業者の使命である。
ソーシャルメディア事業者は消費者から上がってくるコンテンツの整理や誘導、インセンティブの提供、たとえば、
コンテンツにランキングをつけたり、ジャンル事に整理分類したり、コンテンツを販売(書籍化など)する際の仲介役を務めたり、ということに専念することが大事である。
マスメディアの3つの力
- 2009-04-08 (水)
- 社長BLOG
1.制作力
コンテンツを作りだす能力。新聞やテレビの記者による取材記事、社説、お天気お姉さんから、局アナまで、メディア事業者から生み出された物をさす。
2.配信力
コンテンツを配信する能力。新聞や折り込みチラシを配布したり、電波に乗せて、映像や音声を多人数に提供すること。
3.信頼
長期間マスメディアを運営してきた信頼。「100年の歴史のある●●新聞に載っていれば、それは事実」という消費者の意識。
これまで独占的、強大な配信能力に支えられているおかげで、マスメディアは発展してきた。
最近、テレビや新聞の元気がなくなってきたのは、配信力が独占的ではなくなり、特に新興メディアに対し相対的に力を失ったことが原因だ。個人でもWEBと検索サイトの組み合わせで、マスメディアと同等以上の強力な配信能力を手に入れることができるようになった。ネットの進化は止まることが無いので、こうして失った配信力の地位はもう取り戻すことができない。
マスメディアは、2.配信力の優位は失われたので、これからは1.制作力ないし3.信頼で頑張っていこうということになる。
3つのメディア
- 2009-04-07 (火)
- 社長BLOG
SNSでソーシャルメディアだ!という話が増えている。
原理原則が好きな自分としては、そもそも論として、ソーシャルメディアにいたるまでのメディアの変遷について、考えてみたい。
1.マスメディア
2.インタラクティブメディア
3.ソーシャルメディア
1.マスメディア
いわゆる新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどのメディア。
不特定多数に安価で情報を配信することができる。
メディア事業者=>消費者への単方向通信であることが特徴。
2.インタラクティブメディア
メディア事業者と消費者の双方がコミュニケーションできるメディア。
メディア事業者=>消費者への通信が太く、その逆が細いことが普通。
「テレビにおけるテレゴング」
「ラジオにおけるはがき職人」
「雑誌における読者投稿」
のような位置関係。消費者からの登り通信が増えすぎるとメディア事業者がパンクしてしまうため、あえて細めにしている。
3.ソーシャルメディア
情報発信の主役がメディア事業者ではなく、消費者からの発信になるのがソーシャルメディア。
SNS、pixiv、Youtubeなど一方の消費者が作ったコンテンツを、もう一方の消費者が楽しむというコミュニケーション構造。
メディア事業者は、原則コンテンツはつくらない。
どれがいいか?というのはまた別の話。
※サーバダウンしてからブログが書けなかったのですが、再開します。
ETCが手に入らない!
- 2009-03-24 (火)
- 社長BLOG
補正予算も通過してETC助成金がつくらしいし、自分が好きなアクアラインを渡る料金も激安になるらしい。
ということで、この連休に自分の愛車(水色Fit)にETCを取り付けようとカーショップに問い合わせてみたが、オートバックスもカレッツァも、近所のお店はETC売り切れ中とのこと。
とても残念である。
用意しておいておくれよ。。
もしOpenPNEで政策提言SNSが作られていればすぐに入って、議論していると思う。
【社内SNS研究】日立さんのSNS「COMOREVY(こもれび)」とは!?
- 2009-03-23 (月)
- 広報ブログ
こんにちは。
広報の白石です。
スギ花粉飛来もどうやらそろそろ終るみたいですね!
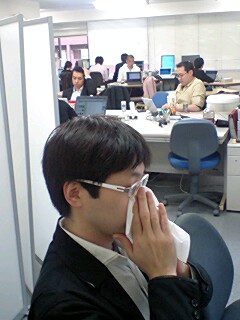
【鼻をかみ続ける長谷川】
目をこすったり、鼻をかんだりしている花粉症の私も営業の長谷川も、
そのニュースに大喜び。
しかし、それもつかの間、今度は、ヒノキ花粉が全盛期になると聞き、
打ちひしがれています。
●日立さんにお話をききました
さて、花粉には泣かさっぱなしの私たちですが、嬉しいこともありました。
以前から社内SNSにOpenPNEを採用し、ばりばり使っていただいている
日立さんに一度、お話を聞きたいな~と思っていたら、たまたまユーザー会の
メンバーさんが紹介してくれたのです。
さっそく手嶋と長谷川にくっついて日立さんのオフィスに行ってきたのですが、
運営者の方々に、とてもおもしろいお話を聞くことができました!
ちょっとご紹介すると…まず、最初からSNSを日立グループ全体を対象に
導入したのではなく、まず、2006年末から日立総合計画研究所(日立総研)だけで、
OpenPNEを使った社内SNS「ミネルヴァの梟(ふくろう)」を実験的に立ち上げ、
使ってみたそうです。
その結果、情報の流通やコミュニケーションの活性化に効果があり、2008年1月から
日立グループ全体を対象にしたSNS「COMOREVY(こもれび)」をスタート。
COMOREVY…SNS内の投票で決まったそうですが、かっこいい名前ですね!
ちなみに、日立グループといっても、何社あるのかお聞きしたら国内だけで、
418社にもなるのだとか。
●登録者は8000人以上!
開始から1ヶ月で2500人の参加があり、1年と2ヶ月たった現在、約8300名の方が
登録しているようです。
巨大SNSの1日のページビューは、なんと14万!
強制ではなく、招待制(自己申告もOK)で、口コミで広がったそう。
コミュニティは370ほどあり、なかでもQ&Aコミュ「応えて、こもれびー」が
業務に役立っているのだとか。
印象的だったのは、例えば九州から関東のA県に転勤になったBさんが、
「A県ってどんなとこ?」と書き込むと、A県に勤務している社員さんから、
子供の学校から病院、はてはゴミの出し方や飲み会のお誘いまで
書き込みがあったそうです。
なるほど、これなら家族を連れて知らない土地に暮らす不安も和らぎます。
転勤する前から飲み仲間?ができるなんて心強い!
●25万人に増えても大丈夫!?
大変、しっかり使っていただいて、開発元としては嬉しい限りです。
逆に日立さんからは、こんな質問をされました。
日立さん 「OpenPNEって、どのくらいまで増えて大丈夫なんですか?
うちは国内でも25万人働いているので…」
長谷川 「たまーに『OpenPNEは8千人超えると止まるの?』と聞かれることも
あるんですが、増えても問題ないですよ~」
手嶋 「すでに23万人が参加しているSNSもありますが、
ちゃんと動いていますので…」
日立さん 「ああー、それを聞いて、今日はほっとしました」
ええ、安心して、どんどん参加者を増やしてください!
まだまだたくさんのお話を聞いたのですが、詳しくは、日経ネットに掲載された
コラムを読んでみてください。運営の参考になると思います。
OpenPNE 開発者流のソースコードの追い方 #3 – vim + ctags 編
- 2009-03-22 (日)
- 開発者ブログ
開発チームの海老原です。
仕事で疲れた日もソースコードを追えばたちまち元気になりますよね! ということで今回も技術ネタです。
ソースコードを追うための必需品といえばやはりエディタです。
そんなわけで今回はエディタを使ってソースコードを追っていきましょう。
ちなみに僕は開発でもバリバリに Vim を使っているため、ここでは Vim (version 7.2) 前提で解説します。
他のエディタを使われている方は適宜読み替えてください。
■ Ctags を導入する
今回は Ctags を使います。 Ctags はソースコードなどから識別子のタグファイル(インデックスファイル)
を生成するプログラムです。おそらく Unix 系 OS には標準で含まれているはずです。
お使いの環境に入っていない場合は以下のようなコマンドによって入手してください(例は Debian)。
# apt-get install ctags
Ctags には Exuberant Ctags や Etags、 gtags などといった派生版も存在します。
どれを使っても基本は同じですので、お好みのものを選んでください。
Ctags を導入したら、プロジェクトのルートディレクトリで以下のコマンドを実行してください。
$ ctags -R
これで tags というタグファイルが自動的に生成されるはずです。
以下のように指定することでタグファイルの対象を限定することもできます。(これについてはまた後日)
$ ctags –langmap=PHP:.php
■ Vim からタグファイルを読みに行く
Vim にタグファイルの場所を教えます。
$HOME/.vimrc に以下の設定を追記してください。
set tags+=tags
■ いざタグジャンプ!
Vim でソースコードを開き、定義を知りたい識別子にカーソルを合わせ、
Ctrl + ]
をタイプしてください。
これだけで定義元にジャンプすることができます。
これはすごい! 便利! それに速い!
ジャンプ前に戻りたい場合は
Ctrl + t
をタイプしてください。
これさえマスターすれば、巨大なソースコードであっても充分読んでいくことができます。
……とはいえ、 Ctrl + ] は正直言って打ちづらいです。
タグジャンプは頻繁に使っていくものなので、ちょっとこれはなんとかしたいところです。
ということで、海老原は以下の設定を $HOME/.vimrc に書いています。
map t
これで、 t をタイプするだけでタグジャンプできます。もうやみつきです。
■ 識別名を直接指定する
定義を知りたいクラス名などがカーソルを合わせるでもなく分かっている場合、あなたならどうしますか?
ここでソースコード検索をしたり諦めて API リファレンスに逃げたりしてしまう方に朗報です。
おもむろに Vim を開き、以下を入力してください。
:tag 【識別名】
すると、指定した識別子の定義元にジャンプすることができます。
これまた便利です。
さらに、指定する識別子は tab で補完することができます。
op*Form というような曖昧な指定もばっちりサポート!
■次回は?
ctags で生成することのできるタグファイルについて深く突っ込んでいきます。乞うご期待!
それではみなさん、今日もハッピーなコードリーディングライフをお過ごしください!