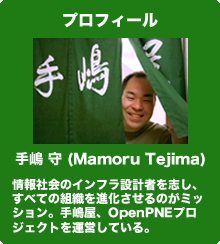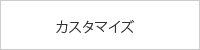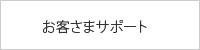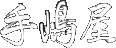社長BLOG
地震に伴う、節電協力のお願い
- 2011-03-12 (土)
- 社長BLOG
今回の地震の影響で発電設備に大きなダメージがありました。首都圏の電力供給に支障をきたしています。特に原発の復旧には時間がかかり、今後長期間の電力不足が予想されます。
ぜひみなさまに、節電の協力をお願いします。
特に光や熱に関わる電気設備が、多くの電力を使います。
照明をなるべく控える。エアコンやホットカーペットの代わりにガスや灯油のストーブを使うなどが有効だと思います。
※他の手段も、メディアなどで伝えられると思いますので、ぜひ参考にしてください。
手嶋屋は、普段電気のおかげで仕事をさせてもらっています。
少しでも力になり、政府、電力会社が停電や原発の復旧に専念できるように、協力をしたいと思います。
よろしくお願いします。
東京電力からの発表
http://www.tepco.co.jp/cc/press/11031217-j.html
関東在住者の過ごし方(節電含む)
http://d.hatena.ne.jp/next49/20110312/p1
Amazon EC2 TokyoにOpenPNE3.6 Betaをインストールする
- 2011-03-10 (木)
- 社長BLOG
ついにやってきたAmazon EC2の東京データーセンター。
早速ここにOpenPNE3.6 Betaをインストールする。
なお、インストールのスピードを速めるために、手嶋がサンプル開発しているExpress版で説明をする。
Express版は手軽にOpenPNEを試してもらいたいために作成している。
正式な運用では公式サイトのOpenPNE3を利用してほしい。
◆マシンの起動
EC2では立ち上がっているマシンをインスタンス(Instance)と呼ぶ。まずこれを起動する。
OSのイメージは、たくさんあってよく分からないが、EBS Centos 64bit Base をキーワードに探してほしい。
自分はこれを選択した。
※Centosと検索して、RootDeviceをクリックしてソートするとすぐ出てくる。

・Microインスタンスを選択。
2ページ目3ページ目はすべてデフォルト。


4ページ目でキーペアを選択
この鍵でサーバにログインするので、作ってなければ新規に作成する。
公開鍵はサーバに自動でセットされる。
秘密鍵はアクセスするパソコン側に保存する。

最後がセキュリティグループの設定。デフォルトで全部塞がれているので、必要なポートを開放してあげる必要がある。

だいたいこんな感じで開放する。

そして起動する。
◆SSHでサーバにアクセス
インスタンス一覧画面でConnectを選択すると、以下のような画面でアクセス方法をおしえてくれる。

指示にしたがってTerminalからSSHコマンドを発行。
xxxxxxxx.pemは先ほどダウンロードした秘密鍵のこと。
ログインできれば、ここからあとは普通のレンタルサーバと同じだ。
◆ミドルウエアのセットアップ
OpenPNEを動かすための下準備、ミドルウエアをセットアップする。
何度も書いているので、ここはコマンドだけ。
yum update
rpm -ivh http://nog.dino.co.jp/dist/centos/5/dino/noarch/dino-release-1.0-1.noarch.rpm
yum -y install httpd mysql-server postfix aspell curl gmp libxslt wget httpd-devel php-5.2.11 php-cli-5.2.11 php-devel-5.2.11 php-pear-5.2.11 php-mbstring-5.2.11 php-pdo-5.2.11 php-mysql-5.2.11 php-gd-5.2.11 php-mcrypt-5.2.11 php-xml-5.2.11
yum -y remove sendmail
yum update
adduser admin
chmod 755 /home/admin
mkdir /var/www/sns
chown admin. /var/www/sns
Apacheの設定も変更する
/etc/httpd.conf の最下行を変更
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin tejima+admin@gmail.com
DocumentRoot /var/www/sns/SITE.NAME/web
ServerName SITE.NAME
ErrorLog logs/SITE.NAME-error_log
CustomLog logs/SITE.NAME-access_log common
<Directory /var/www/sns/SITE.NAME/web>
AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>
/etc/init.d/httpd start
◆OpenPNEのインストール
今回は手間を省くために、Express版を使う。ここで管理している。
※正式リリースではないので、セキュリティなどを完全には考慮していません。実運用は控えてください。
https://github.com/tejima/OP3express
「ダウンロード」からTP2.zipを選択する。
サーバから以下のコマンドで取得する。
su – admin
mkdir /home/admin/OpenPNE
cd /home/admin/OpenPNE
wget –no-check-certificate https://github.com/downloads/tejima/OP3express/OpenPNE3-mini-TP2.zip
unzip OpenPNE3-mini-TP2.zip
cd OpenPNE3
インストールコマンドは以下のとおり。
※ネットワークに接続しないで、SQLite版でインストールする
./symfony openpne:install –standalone –sqlite
メモリが足りない!
/etc/php.ini の memory_limit を 128Mに変更する。
再びインストールコマンド。今度は成功する。
シンボリックリンクの作成
WebサーバApacheからは/home/adminではなく、/var/www/sns/SITE.NAMEを参照させる。
以下のようなコマンドでシンボリックリンクを作成
cd /var/www/sns
ln -s /home/admin/OpenPNE/OpenPNE3 SITE.NAME
あとはブラウザからSITE.NAMEを開けばOK。
Express版の場合、以下のような画面が出れば成功だ。

Expressで一度インストールを成功させておくと、正式版のOpenPNE3のインストールも簡単になるとおもう。
OpenPNE3 Betaはミドルウエアや運用環境の違いに寄って、インストールが止まることがよくあるので、
もし詰まったら、段階を踏んでインストールすることをおすすめする。
02/26 WebMatrix Day@品川 イベントレポート

イベントのレポートが技術評論社のサイトから上がってきた。
参加したイベント情報はこれ
http://gihyo.jp/event/2011/webmatrixjp
自分が参加したセッションの内容はこちら。
パネルディスカッション─オープンソースを活用してWebサイト開発を簡単にするためには
Windows環境で手軽にOpenPNEを運用できるようになるということで、今回のセッションはビジネスを強く意識した作りになっている。
OpenPNEが普及した社会では、もはやオフィスは必需品では無い
ということを、強くアピールした。
そして自分は「旅人ワーカー」になりたい。
5人で1人を演じるアプローチ
- 2011-03-01 (火)
- 社長BLOG
「滅私奉公は日本のお家芸」という言葉がある。
私を滅して公のために奉じるという意味だが、感覚的に同意できるところが多いのではないか?
最近だと伊達直人が有名だ。個人名でも、無記名でもなく、伊達直人と書いて寄付するあたりがとても日本的な気がして素敵だった。
このよさをソフトウエアに込めることができないか?
OpenPNEで考えてみる。
OpenPNEの中の複数人で一人の人格を演じる
というのはどうだろうか?
TwitterやFacebookなどの巨大なソーシャル・ネットワークの中で、個人が立ちまわるのは少々大変だ。
Twitterの中の「伊達直人」を複数人の支援者で演じることができるように、OpenPNEを改造するのは面白いかもしれない。
OpenPNEの中には5人の活動者がいる。その5人が持ち回りでひとつのTwitter上の人格「伊達直人」を演じるのだ。

パーティー会場の中にオフィスをつくる
- 2011-03-01 (火)
- 社長BLOG
手嶋屋は忙しい。
社員の歓迎をしたいのだが、集まれないことも多い。
パーティ会場の中にオフィスを作れば、メンバーはいつでもイベントに参加できるのではないか?
と考えた。
普通のオフィスだと床がOAカーペットになっていて、水物をこぼす心配があるのでやりにくい。
ドコモが4月からSIMロック解除–で、何が変わるの?:CNETパネル
- 2011-02-25 (金)
- 社長BLOG
CNETオンラインパネルへ回答した。
「ドコモが4月からSIMロック解除–で、何が変わるの?」
SIMロック解除で、DocomoでiPhoneが提供されるようになることが、一番大きなインパクトでしょう。Docomoはこれから、「俺らが解除したんだから、SoftBankも解除しろ(させろ)」と総務省に対して一生懸命圧力をかけるでしょう。これはどんどんやって欲しい。
さて、SIMロックの日本的事情について少し解説します。携帯には大きく言って3つの要素(通信回線、端末、コンテンツサービス)があり、通常海外ではそれぞれ別々の会社が担当しています。
日本が特殊(ガラパゴスと言われるゆえん)なのはこの3要素を、キャリアがすべてコントロールしていたこと。携帯普及初期にこれがよい方向に働きました。当時3要素のすべては黎明期、発展段階であり、それぞれが日進月歩で進化していきます。これらの要素を融合させたサービスを生み出すスピードは、日本が最速でした。たとえば通信回線を速くし、動画再生機能つき携帯を大量に安価で販売したうえで、動画コンテンツを提供する。もっと古くは、写真つき電子メール(写メール)も、回線と携帯端末が非常に密接に連携して提供されていました。
残念なのは、普及期にはこの戦略はいいが、成熟期にはデメリットになること。日本の特殊事情に合わせすぎて、端末メーカーとコンテンツサービスに世界的な競争力を持つ企業を生み出すことができなかったことです。
SIMロックはこの3要素の密接な連携を後方支援していた、と考えることができます。
私はSIMロックに限らず、国が保護や規制をかける場合は「将来外貨を稼ぐことを目的として、その企業を成長させるために規制する」と方針を定めなければなりません。携帯の規制では、消費者に負担をかけていると思います。負担とは、高い回線、使いづらい端末、割高なコンテンツサービスです。世界で活躍できる企業を生み出せなかったことも、間接的には負担でしょう。
日本の携帯会社が携帯の分野で、これから海外に打って出るのは不可能だと思います。以後は消費者の負担を下げる方向に徹底的にコントロールを進めて欲しいです。
「居場所」という言葉がOpenPNEには合う
- 2011-02-22 (火)
- 社長BLOG
手嶋屋のスタッフの酒井さんが、「OpenPNEの一番いいところは、すぐに居場所を提供できるところだと思う。」というような話をしてくれた。
OpenPNEの目的やキャッチコピーは常に考えているのだが、自分が考えるとどうしても堅くなってしまう。
「組織」とか「進化」とかそういった言葉ね。
実際に使ってくれている運営者にとっては、簡単に居心地のいい居場所を作るためにOpenPNEを使っている。
というのが、一番素直なのではないだろうか?
この言葉に、加藤登紀子さんもすぐさま反応してくれた。
http://twitter.com/#!/TokikoKato/status/37768005047947264
大きなSNSには自分が安心できる居場所がない。マイノリティには居場所がない。地域には居場所がない。
だからOpenPNEを使ってくれているんじゃなかろうか。
いくら大きなソーシャルネットワークがやってきても、だからといってそれが居場所になるとは限らない。
われわれはあらたな「居場所」をつくっている。
居場所というとこぢんまりとした印象があるが、ネットは広大である。
日本国民全員が参加する居場所なんてものがそのうちできてしまうかも知れない。
02/26 WebMatrix Day@品川 に参加
WebMatrix Dayのイベントがいよいよ今週末に迫ってきた。
http://gihyo.jp/event/2011/webmatrixjp
「OpenPNEがあれば(Officeは要るけど)オフィスは要らない」
というタイトルで50分間のセッションを担当する。
OpenPNEはネット上に会社や学校などの組織の”居場所”をつくりだすことができるソフトウエアである。
今回は会社組織の”居場所”をOpenPNEでつくるステップを、具体的に説明していく。
会場はマイクロソフトの品川の新オフィスになる。
100名限定申し込みは金曜朝までとのこと。ぜひご参加いただきたい。
http://gihyo.jp/event/2011/webmatrixjp
手嶋屋でOpenPNEを学ぼう
- 2011-02-22 (火)
- 社長BLOG
春休みの腕試しに、手嶋屋でOpenPNEを勉強しませんか?
高校も大学も、そろそろ受験が終わるシーズンではないか。
手嶋屋にも高校三年生の木村くんがインターンとして参加した。
木村くんは手嶋屋トライアルの合格者で、試験を受けた高校2年生という年齢は当時の最年少記録だった。
(現在は高校1年生かしわさんが最年少記録)
手嶋屋トライアルは、Linuxサーバを提供して、OS、ミドルウエアの設定から、OpenPNEのプラグイン開発までの一連のタスクをチェックポイント形式で突破する、実践的な内容になっている。
合格者には手嶋屋でのインターン参加権が得られる。
興味があれば、@tejima まで直接連絡をいただきたい。すぐにトライアルを開始する。
※トライアルはすべてリモートで実施可能です。
02/05 地域SNS研究会@静岡掛川

先週の土曜、日曜と地域SNS研究会に参加した。
以下は地域SNS研究会のレポート。
http://www.glocom.ac.jp/project/chiiki-sns/2011/02/sns_91.html
自分が発表したのは、ソーシャル・ネットワーク運営の際の技術力の必要性。
「コミュニティ運営能力」「技術力」「資金力」の三つが必要だが、地域SNSは特に技術力が足りない。
われわれの技術力が圧倒していれば、使いやすいサイトになるのだが、
OpenPNEは地域向けに専用で作られているわけでは無いのでどうしても不足してしまう。
こうした足りない部分を、改良して使ってもらえるとうれしい。
「自分の子どもにプログラミングを教えるか?」というイメージを持っている人が少ない。
たとえば「自分の子どもに、犬小屋づくりを教えますか?」というと、少なくとも想像ぐらいはするだろう。
テクノロジーは、世の中を幸せにこそすれ、不幸せにするものではない。
地域で豊かに暮らすためのテクノロジーは、どんどん研究すればいいのだ。
研究会開催の地、掛川は大変興味深かった。メインはお茶で有名なのだが、二宮金次郎で有名な「大日本報徳社」という会社もある場所だ。掛川市は「生涯学習の町」として、20年近くの歴史があるとのこと。
そこで自分が得たのは「勤勉」という言葉。素敵な言葉だ。
掛川市では「生涯学習」という言葉を使っているようだが、それは少し古い気がしたのでシンプルに「勤勉」でいいんじゃないかと思う。
※写真は二宮金次郎像シニアバージョンだ。かなりレア。
以下は今回の研究会で撮影した写真。
http://www.dropbox.com/gallery/151520/1/20110207KAKEGAWA?h=1d28df