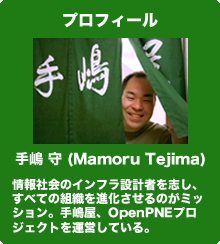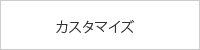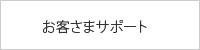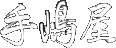社長BLOG
「伽藍とバザール」×「尖閣諸島問題」
- 2010-09-25 (土)
- 社長BLOG
オープンソース開発者はみんな読んでいる「伽藍とバザール」
オープンソース業界の古典だ。
※まだ読んでなかったら、無料なので必ず読んでみて欲しい。
この本はプログラムのことだけが書かれているだけでなく、経済やモノの価値、人間の業やモチベーションについても指摘されていて、ビジネスモデルやコミュニティ運営までも含めて、OpenPNEプロジェクトを立ち上げる際にとても役に立った。
伽藍とバザールの第二弾「ノウアスフィアの開墾」では、土地の所有権についての考察もされている。そこでは土地の所有権を手に入れるには3つの方法がある、と言っている。
1:未開の地の開墾
2:土地所有権の移転
3:占拠
今の日本では基本的に2:しか考えられない。
日本にはほとんど未開の地はないし、(あったとしても埋立地くらいか?)
土地の所有権は法律に基づいて移転されている。
今回の尖閣諸島問題では、ひとつの土地に対して2者(日本と中国)が互いに所有権を主張している状態だ。こうなると2:で決着することは殆ど無く、3:の手段をとることになる。占拠のやり合い。漁船が入って捕まると言うのは、占拠のためのつばぜり合いをしていることになる。
自分は本能的に考えると、太古の昔「ナワバリ」の時代から始まっているので、法律的に土地の所有権が決まるという現代の感覚の方にこそ違和感がある。
今回の問題については、土地にしばられない情報社会を自分はつくろうとしているので、あまり気にならない。
それでも、日本にはあと100年ぐらいは現状維持で行って欲しいと思う。
※伽藍とバザールはドキュメントの二次利用が自由なので、第五章を全文掲載する。
5 ロックと土地所有権
この生成パターンを理解するには、ハッカーの通常の関心領域をはるかに離れて、こうした慣習と歴史的に類似した例を見るのが役に立つ。法制度史や政治哲学を学んだ人ならお気づきのように、ハッカーたちが暗に主張している所有理論は、英米慣習法における土地所有権の理論とほとんどまったく同じなんだ!
この理論では、土地の所有権を獲得する方法は3つある。
未開の地(フロンティア)には、これまで所有者のいなかった土地がある。そこでは人は、開墾(homesteading)することで所有権を獲得できる。つまり、自分の労働を所有されていない土地に混ぜ込み、囲いをつけて自分の地権を守ることによって。
入植済みの地域での土地移譲は、ふつうは土地所有権の移転によって行われる。これはつまり、前の所有者から証書を受け取ることだ。この理論に基づけば、所有権の連鎖という概念が重要になる。所有権の証明として理想的なのは、証書とその移転の連鎖が、その土地のそもそもの開墾時点にまでさかのぼれることだ。
最後に、慣習法理論は土地の所有権が失われたり放棄されたりすることがあるのを認識している(たとえば所有者が相続人なしに死んだり、空き地に対する所有権の連鎖を確立するための記録が失われていたりする場合)。このようにして遺棄された土地は、占拠によって所有権の主張を行える――だれかがそこに入居して、整備を行い、そして開墾時と同じようにそこの所有権を防衛するわけだ。
この理論はハッカーの慣習と同じように、中央権力が弱いか存在しないような場面で有機的に発達してきた。それは千年以上もかけて、ノルウェイやドイツの部族法から発展してきたものだ。それを近代の初期に体系化して合理化したのがイギリスの政治哲学者ジョン・ロックだったので、これはよく所有物の「ロック」理論と呼ばれる。
論理的によく似た理論は、ある物件が経済的または生存上で高い価値を持っていて、しかも稀少財の配分について、中央集権的に強制するだけの力を持った単一の権威が存在しないところでは必ず生じるようだ。これは、ときどきロマンチックに「所有」の概念がないと考えられたりもする狩猟採集文化でも成り立つ。たとえば Kgalagadi (カラハリ) 砂漠のクンサン・ブッシュマンの伝統では、狩猟場には所有権は存在しない。でも、井戸や泉については所有権が存在して、その理論は明らかにロックの理論と似ている。
クンサン・ブッシュマンの例は示唆的だろう。というのも、これはロック式の所有権慣習が、その資源からの期待リターンがそれを独占して守る期待コストよりも大きい場合にのみ生じることを示してくれるからだ。狩猟場が所有権の対象にならないのは、狩猟のリターンがすごく予想しにくくて変動しやすく、さらに(すごく高く評価はされるけれど)日々の生存にとって絶対的に必要なものではないからだ。一方の井戸は、生存にとって不可欠だし、守りきれるくらい小さい。
この論文の題名に出てくる「ノウアスフィア(noosphere)」というのはアイデア(観念)の領域であり、あらゆる可能な思考の空間だ[N]。ハッカーの所有権慣習に暗黙に含まれているのは、ノウアスフィアの部分集合の一つであるすべてのプログラムを包含する空間での、所有権に関するロック理論なんだ。だからこの論文は「ノウアスフィアの開墾」と名付けた。新しいオープンソース・プロジェクトの創始者がみんなやっているのがそれだからだ。
Fare Rideau (rideau@ens.fr)}は、ハッカーは純粋観念の領域だけで活動しているとはいえないと指摘している。これは正しい。かれの主張だと、ハッカーが所有しているのはプログラミング・プロジェクトなんだ―― これはつまり、物質的な労働(開発、整備など)の意図的な焦点で、ここに評判、信用性なんかが結びついている。ここからかれは、ハッカーのプロジェクトが覆っている空間はノウアスフィアではなく、むしろその分身のような、ノウアスフィアを探索するプログラム・プロジェクトだと主張する(読者のなかの天文物理学者たちに敬意を表しつつも、語源的にいえばこの分身空間を「エルゴスフィア」または「作業のスフィア」と呼んでまちがいない)。
現実問題としては、ノウアスフィアとエルゴスフィアとの区別はこの論文の目的からいえばだいじじゃない。Fare が主張するような純粋な意味での「ノウアスフィア」が、なんら意味あるかたちで存在すると言っていいのかは、実はよくわからない。そんなものを信じるには、プラトン主義哲学者にでもなるしかないだろう。そしてノウアスフィアとエルゴスフィアとの区別が実際的な重要性を持つのは、アイデア・観念(ノウアスフィアの要素)は所有できずそれをプロジェクトとして実体化したものだけが所有できると考えたい場合だけだ。この問題から出てくる課題は、知的所有権の理論的な問題につながるもので、この論文の範囲を超える。[DF]
でも混乱を避けるために言っておくと、ノウアスフィアもエルゴスフィアも、時に(多くのハッカーたちは顔をしかめるけれど)「サイバースペース」と呼ばれる電子メディア内での仮想位置全体とはちがう。サイバースペースでの所有権はまったくちがった規則にしたがって統制されている。その規則は物質的な世界での規則のほうに、むしろ似ている――基本的には、その「サイバースペース」の一部を宿しているメディアやマシンを所有している人物が、そのサイバースペースを結果的に所有していることになる。
ロック的な構造は、オープンソースのハッカーたちがその慣習をまもるのは、なにか自分たちの努力からの、一種の期待収益を守ろうとしているからだろうと強く示唆している。この収益は、プロジェクト開墾の努力や「所有権の連鎖」を記録したバージョン履歴を維持するコスト、そして捨て子になったプロジェクトを占拠するまでに公的な通達を出してしばらく待つという時間コストよりもずっと大きなものでなくてはならない。
さらに、オープンソースからの「収益」は単なるソフトの利用価値以上のものでなきゃならない。プロジェクトの分裂によってダメになったり減ったりしてしまうようなものでなければ。もし利用価値だけが問題なら、分裂に対するタブーはないし、オープンソースの所有権も土地所有権とは似てもにつかないはずだ。事実、既存のオープンソース・ライセンスから導かれるのは、こういう(利用価値だけが唯一の収益となる)別世界だ。
いくつか候補としてあがる収益はすぐに却下できる。ネット接続上では有効な脅しがかけられないので、権力追求はまったく成り立たない。同じく、オープンソース文化はお金や内的な稀少性経済に類するものは持っていないから、ハッカーたちも物質的な富とあまり似たものを追求していることはあり得ない。
ただし、オープンソース活動で人々がもっと金持ちになれる方法が一つなくはない――そしてそれは、その実際に動機に貴重なヒントを与えてくれるものではある。しばしば、ハッカー文化で人が獲得した評判は実世界でも反映されて、それが経済的に意味をもってくることがある。もっといい仕事が得られるとか、コンサルタント契約が手に入るとか、あるいは本の執筆依頼がくるとか。
でもこの種の副作用は、よくいってもまれだし、ほとんどのハッカーにとっては副次的なものでしかない。唯一の説明として説得力を持つには、多くのハッカーにはあまりに縁遠いものだ。それにハッカーたちはなんども、自分たちは金のためにやってるんじゃない、理想と愛のためにやってるんだ、と主張している。まあこれは割り引いてきくにしても。
でも、こういう経済的な副作用が処理されるやり方は検討する価値がある。これから、オープンソース文化そのもののなかでの評判の力学だけでも、かなりの説明力があることを見てみよう。
09/24 「OpenPNEはすべての組織のプラットフォームに」
本日PHPカンファレンスでセミナーを講演した。

※TwitPicにあがっていたものを借りました!
OpenPNE Ver3.6の目玉機能「モバイルオープンソーシャル」「リアルタイムWEB対応」「パフォーマンス」を紹介。
OpenPNEのゴールである
すべての組織のプラットフォーム
これを実現するための進化に向けて、Ver3.7の開発系でも着々と進化を続ける予定だ。
こんな話をした。
明日のテックデーもフルタイムで参加する。
※緑色の手嶋屋Tシャツを見つけたら、ぜひ声をかけてください。
09/24 13:35 PHPカンファレンス(ビジネスデー)で講演します
9/24 9/25 PHPカンファレンス2010の初日(ビジネスデー)で講演します。
13:35〜 ルームBにて
~モバイルオープンソーシャルにも対応!~ OpenPNE Ver3.6紹介
というテーマで講演します。
・OpenPNEプロジェクトの紹介
・10月リリース予定のVer3.6の最新機能
・モバイルオープンソーシャルの搭載
・リアルタイムコミュニケーション
・スケーラビリティ
・追加プラグイン
・今後のロードマップについて
以上を中心に話す予定です。
ぜひイベントに参加してください!
mixi meet-upイベントを体験して思ったこと
- 2010-09-10 (金)
- 社長BLOG
会場にはいけなかったが、今回のmixiイベントはUSTREAMとTwitterで体験させてもらった。
Facebookと同じオープン化戦略という印象が一番強かった。
個人的な思いは、
今回mixiオリジナルのイノベーションは何だったのか?
ということ。ソーシャルグラフの開放、APIの提供、他社との提携。
いろいろすてきな発表はあったが、自分の感覚ではイノベーションと言えるものはなかった。
※流行る流行らないという軸とは全く別ね。自分がイノベーションを驚き、感動できるか?という視点。
自分が2004時点の最初のmixiに対して、これらのイノベーションに心底感動した。
・自分と、フレンド、コミュニティが同じレイアウト
・ROMをコンテンツに変えてしまう、魔法のあしあと
・毎週イベント、女性が使っていることを普通に言える出会い系サイト
だった。ここに他意は無い。全て心から素晴らしいと思っている。
今回のイベントで語られていたことは、ほとんどがFacebookのイノベーションであり、Twitterのイノベーションだった。
自分は、あしあとやレイアウトに続くイノベーションを期待していたのだ。
そんなことを考えて自分のブログを探してみたら、4年前にもmixiの変化というブログで、同じようなことを、記事に書いていた。
イノベーションは、自分がOpenPNEで起こす。
「もしドラ」かぶり
- 2010-09-10 (金)
- 社長BLOG
もしドラといえば
「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら 」
でも、こんな本も見つけた。
「もしドラえもんの『ひみつ道具』が実現したら タケコプターで読み解く経済入門 」
もしドラえもんだから、略して「もしドラ」だ。両方とも署名が長い。略したくなる。
※ドラえもんの方の作者がTwitterで話していたので、話に参加したら、作者さん本人から薦められました。
ちなみにこの作者さんの本では「スリッパの法則」も読んでいます。
日本語圏でハッシュタグ(#hashtag)は必要ないかも
- 2010-09-09 (木)
- 社長BLOG
Twitterで特定のテーマを話すとき、#+アルファベット形式のハッシュタグを使う。
自分の周りでは、#nhk と入ったつぶやきをよく見かける。
ただしこのハッシュタグにはクセがある。
まず日本語が通らない。#+アルファベットでなければならないので、かなり使いにくい。
海外ではこのように文章の途中の単語としてハッシュタグが登場するケースがある。

こういう使い方ならかなりスマートだなと思った。
最近はハッシュタグをつけなくても検索にうまく引っかかるので、少なくとも日本語圏では、ハッシュタグよりも普通に書いていって、検索すればいいんじゃないか。
ブログ+RSSリーダー=Twitter?
- 2010-09-08 (水)
- 社長BLOG
Twitterにはいろいろな側面があるが、その一つとして
ブログとブログリーダー(RSSリーダー)がセットになったサービス
と考えることができる。
ブログも今まさに書いているところだし、RSSリーダーは自分のようなITマニアに取っては、大量の情報を効率的に読むために欠かせない。
しかし便利でありながら、一般ユーザーまで広がったサービスだとは必ずしも言えない。
RSSリーダーの概念が、操作方法が、登録が非常に面倒だったのだ。
Twitterが登場してから考えてみると、なんで今までブログ投稿画面と、RSSリーダーは一緒になってなかったのか?と不思議に思ってしまう。
ブログ投稿画面

RSSリーダー

この二つをバラバラに登録し、利用していたのだ。
Twitterが出てから考えると、この二つの画面はいかにも使いづらい。
複雑だし、殺風景だし、投稿も、管理も面倒だ。こりゃ一般にまで流行るわけがない。
そりゃ、画像や動画を張り付けたり、複雑な文字装飾を行ったり、何百行にも及ぶ文章を書いたり読んだりするためには、それなりの複雑さが必要のなのはわかる。
それだけに、Twitterの潔さと、便利さは特筆すべきだと思う。
Twitterの画面を見てみよう。

ブログ投稿画面とRSSリーダーの機能が一画面に収まっている。自分で投稿したつぶやきは、RSSリーダーのすぐ上に表示されるから、投稿の表示画面も兼ねている。
ユーザーインターフェースとしてよくできているな、とつくづく思う。
OpenPNE 3.4から 3.6Beta4にバージョンアップ
- 2010-09-08 (水)
- 社長BLOG
OpenPNE3.4から3.6Beta4へのバージョンアップ手順ガイド。
バージョンアップ手順について
バージョンアップの手順は基本的にOpenPNE付属のドキュメントを参考にした。
http://github.com/openpne/OpenPNE3/blob/OpenPNE-3.6beta4/doc/ja/OpenPNE3_Version_Up_Guide.txt
データベースのバックアップ
バージョンアップ前には必ずデータベースのバックアップを取ること。
自分の場合はクラウドサーバを利用しており、OSごとスナップショットを取っている。
※ちなみに今回は、一度メモリーリミットでバージョンアップに失敗しており、スナップショット版に巻き戻した。
php.iniでメモリーリミットを増加
vi /etc/php.ini

今回は256MBにしたら、エラーが発生しなかった。
バージョンアップ途中でのメモリーエラーは、データーベースが中途半端な状態になってしまい、かなり都合が悪い。なるべく余裕を持った設定値にしておきたい。
OpenPNEのダウンロード

リンクアドレスをコピーし、サーバ内でwgetしてダウンロード。
cd /home/admin/OpenPNE
wget http://github.com/openpne/OpenPNE3/zipball/OpenPNE-3.6beta4
unzip openpne-OpenPNE3-OpenPNE-3.6beta4-0-g27edc0f.zip
ファイル名を適切なものにリネームする。
/home/admin/OpenPNE/site.com_3_6
自分はたいていこのようにしている。
設定ファイルの修正
OpenPNE.yml.sample
ProjectConfiguration.class.php.sample
をそれぞれコピーし
OpenPNE.yml
ProjectConfiguration.class.php
を作成する。
cd config/
cp OpenPNE.yml.sample OpenPNE.yml
cp ProjectConfiguration.class.php.sample ProjectConfiguration.class.php
※この時、移動をしてはいけない。sampleファイルとなっているが、OpenPNE側で初期値として利用するので。
Ver3.4のdatabases.ymlをコピー
databases.ymlはVer3.4時代のものをそのまま使う。
旧サーバのファイルを./config/databases.yml としてコピーする。
cd /home/admin/OpenPNE
cp site.com_3_4/config/databases.yml site.com_3_6/config/databases.yml
※旧サーバの設定値を使うということは、旧サーバのデータベースを上書きするということ。絶対にバックアップを取るのを忘れないように!失敗すると取り返しが付かないことになる。
プラグインディレクトリのコピー
Ver3.4時代に使っていた、もしくは追加したプラグインがあるかも知れない。
これらは新しい方にコピーしてあげる必要がある。
cd /home/admin/OpenPNE
cp -aur ./site.com_3_4/plugins/* /home/admin/OpenPNE/site.com_3_6/plugins
cp -aur ./site.com_3_4/plugins/.* /home/admin/OpenPNE/site.com_3_6/plugins
バージョンアップコマンドの実行
./symfony doctrine:build-model
./symfony cc
./symfony openpne:migrate
./symfony plugin:publish-assets
バージョンアップは4つのコマンドを実行することで完了する。
※この途中でエラーが起きたら、データベースを巻き戻してやり直すことをおすすめする。
旧サイト=>新サイトへのシンボリックリンクはりかえ
自分は、プログラムの設置場所とApacheからの参照先を分けている。
Apacheからは常に
/var/www/sns/[ドメイン名]
となるようにhttpd.confの設定を行っている。
したがって今回は
cd /var/www/sns/
rm /var/www/sns/site.com
ln -s /home/admin/OpenPNE/site.com_3.6 site.com
として、旧サイト=>新サイトのリンク張替えをおこなった。
動作確認
すべての作業が完了したら、管理画面にログインして、フッター部分のバージョン表記が

となっていればバージョンアップ成功だ。
※真っ白な画面になってしまったら、web/index.phpの

この部分をfales=>trueに変更し、エラー画面を表示させて原因を探って欲しい。
大抵の場合は、バージョンアップがうまく行っていないと思うので、
バージョンアップ前にロールバックし、バージョンアップ作業を繰り返してみてほしい。
クラウドサーバ比較表【更新中】
- 2010-09-07 (火)
- 社長BLOG
手嶋屋とOpenPNEにとっての福音である、クラウドコンピューティング。
あまりにもバズワード化して乱立してきているので、自分の独断と偏見でまとめて見ることにした。
OpenPNE Ver3で極小規模から500万人レベルの大規模までの運用を行うことをテーマに、
評価軸を設け各社のクラウドサービスを比較する。
今回扱うのはクラウドの中でも仮想サーバを提供するクラウド、いわゆる HaaSやIaaSというものを対象にする。EC2が代表的。GoogleAppEngineのようなプラットフォームや、Gmailなどのサービスは範囲外だ。
運用条件
OpenPNE Ver3.6を使う
ユーザー数100名からスタート。
以後ユーザー数やアクセス、データ量の増減に応じて
・ネットワーク回線
・サーバ構成
・サーバスペック
・サーバ台数
これらの柔軟な構成変更に対応
オートスケールに対応
ソフトウエアからのスケールに対応
エントリー
Amazon EC2
Rackspace
Unit Hosting
Niftyクラウド
参考
さくらのVPS
TrueCLOUD
比較表
クラウドの比較表だけにクラウドソーシングで編集中!
http://bit.ly/aJsQ8R
※以降追記中
10/02 10/03 開催のPHP Matsuri イベントに協賛
PHP Matsuriに協賛した。

PHP Matsuriは2日間に渡って夜通し開催される開発イベント。
手嶋もエンジニアとして参加予定だ。
モチベーションの高いPHPエンジニアと一緒になって、開発をしていきたい。
おそらくイベントでは、OpenPNE関連のプラグインを書くことになると思う。
まだ申し込みを受け付けているので、ぜひ参加して欲しい。