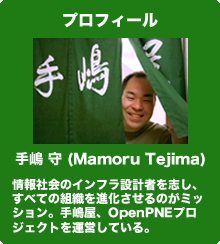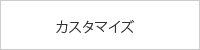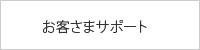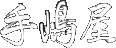社長BLOG
なぜネット対応テレビがうまく行かないのか?
- 2010-09-06 (月)
- 社長BLOG
ネット対応のテレビはこれまでにもたくさん出ている。
アクトビラしかり、パソコン内蔵テレビしかりだ。
今日のニュースでもこのような発表があった。
これがGoogle TVだ! ソニーが11月発売モデルを世界初披露… : ギズモード・ジャパン
http://bit.ly/aD72no
ただ、このこころみも、自分の予想ではうまく行かない。
それはなぜか?
答えは
「テレビ本体の使用年数と、パソコン、ネット部分の使用年数に差があるから」
これに尽きる。(地デジ化需要で少なくなってはいるかもしないが)テレビは平均で8年程度使用する。
一方でパソコンは長くて5年程度。使用年数に違いがあるものを、組合わせてひとつの製品として売ることは相当難しい。
それでも抱き合わせてひとつの製品としているのは、家電メーカーがどうしてもテレビをテレビとして売りたいからだろう。
消費者としてはテレビを「8年使うモニター」として売ってくれるのが一番だ。
8年使えるモニターを買って、4,5年ごとにパソコンを買い直せばいい。
本当はこんなパラダイムはずっと前から当たり前なのだが、
足を引っ張っているのはふたつ。
・家電のテレビ売りたい根性
と
・メディア向けのWindowsのできの悪さ
だ。Widowsは残念としかいいようがない。一番ひどいのはリモコン。
これ。
一応メディア用に設計されているのだが、対応アプリケーションがほとんど無いのと、一部キーボードやマウスに頼らなければならないので、ソファーでゴロンというわけには行かない。(たまに、キーボードに寄らないといけない)。
それなら、潔く、このような製品にすればよかったのだ。
フルキーボードでタッチパッドも搭載している。
残念なWindows側は、AppleやGoogleががんばってくれる可能性はあるが、使用年数の差はどうにもならない。ネット対応テレビはうまく行かない宿命を背負っているのだ。
「OpenPNEが組織そのものになる」EGMサミットでの気付き
- 2010-09-04 (土)
- 社長BLOG
「今いろんな組織(メーカー、企業、自治体、メディアなど)がSNSに対して行っていることは、情報組織、情報社会というゴールにたどり着くための試行錯誤なんだ」
ということ。
これは自分がOpenPNEプロジェクトで常に意識している
「OpenPNEが組織そのものになる」
という設計思想に起因している。サミットに参加し、あらためてこの思いを深めた。
EGMサミットは主に大企業の従業員が集まって、社内SNSのあり方について語り合うイベントだ。
ある会社では、福利厚生の道具として業務以外の使い方を奨励し、またある会社では、積極的に業務の中に取り入れようと努力している。
参加者の属性もまちまちで、自主的に参加する社員の一部だけが参加するケースもあれば、全従業員を強制的に参加させるケース(手嶋屋もそう)、社員管理システムとID連携をして自由にログインできるようにしている会社もあった。
そこで自分は「その社内SNSのゴールはなに?」と思った。なんだかどれもゴールがよくわからないのだ。
半年ほど前に地域SNSのイベントに参加した時も、同じような感覚を持った。
地域SNSの場合は、企業のSNSと同じように目的はなにか?誰が入るか?という要素に加え、誰が運営するか?どこまでのメンバーを対象とするか?という新たなパラメータが加わり、さらに複雑になる。
地域SNSのイベントにも、ゴールのヴィジョンが必要なんじゃないか?と、当時思っていた。
この二つのイベントに参加して、特にEGMサミットに参加して、改めて確認したのが
「今いろんな組織(メーカー、企業、自治体、メディアなど)がSNSに対して行っていることは、情報組織、情報社会というゴールにたどり着くための試行錯誤なんだ」
このこと。
組織が取り組むSNSのゴールは、情報ネットワーク上に組織そのものをつくること。これ以外のゴールは無いと信じている。
今はまだ、参加者の発想がリアルに寄り過ぎているのではないかな。オフィスはあるよな、工場はあるよな、仕事は机の上でやるもんだよな。という感覚を持った上で議論をしている。すなわち、軸足をリアル側においた上で議論や改善を進めているんだ。
一度これらの概念を取り去り、会社がSNSそのもので、会社の組織活動はすべてSNS上で行われると、考えてみて欲しい。バーチャル側に軸足をおいて、そちら側から社内SNSのあり方や設計を考える。
自分はOpenPNEの設計者の一人として、そのゴールは「OpenPNEが組織そのものになる」であると確信している。
好き嫌いにかかわらず、組織のバーチャル化は進み、ネットワーク上で組織の活動をするようになる。合理的に考えてそこから逃げるよりも積極的に取り組んでいったほうが得が多いと思う。
でも、どうせなるなら、人間らしく楽しいものを作りたいとも思う。その設計にしても、がさつなグローバルスタンダードではなく、日本の組織の繊細な部分も表現できる仕組みをつくりたい。そんな気持ちでOpenPNEを設計している。
自分のコンセプト「OpenPNEが組織そのものになる」は間違ってないと感じた。
ネイティブIDはマスタとの連携でつくる【OpenPNE設計案】
- 2010-09-03 (金)
- 社長BLOG
ネイティブIDとゲストIDの話をした。
IDを発行するのは利用者にとっても運営者にとっても負担の大きい業務だ。できればやりたくない。
であれば、すでに組織によって作成、管理されているID体系をそのままネイティブIDとして使えればいいという考えにたどり着く。
そこで登場するがID連携。
大抵の企業は社員番号とメールアドレスの@以前の部分を管理している。
これらすでに発行されたIDを、OpenPNEにおける基本のID(ネイティブID)として、使うことができれば、組織を構成するSNSにとって非常に使い勝手がいい。

実際の連携はLDAPやActiveDirectoryなどで構成される社員のマスタとOpenPNEをつなぐことで実現する。OpenPNEの認証プラグインを拡張することで対応可能だ。現在のOpenPNE3では、認証プラグインを使うことでOpenID や GoogleAppsを外部の認証機構として利用することができる。
社員名簿とOpenPNEアカウント
学籍番号とOpenPNEアカウント
ゲームアカウントとOpenPNEアカウント
これらを連携すると便利。
ゆくゆくは住基ネットや免許証、今度できあがるらしい国民IDともOpenPNEを連携させていきたい。
「ネイティブIDはマスタ連携でつくる」が、今日のポイントだ。
09/02 symfony×OpenPNE3勉強会のまとめ(@Nifty会議室)
「9/2 OpenPNE3で学ぶsymfony勉強会@Nifty(19:00〜)」の開催レポート。
セッションの資料を共有する。
※手嶋以外のスピーカー資料も手に入り次第、本ページを更新します。
1. 「OpenPNEのモバイル機能とsymfony」スピーカー:手嶋守
日本で生まれたOpenPNEは、モバイルへの対応が充実しています。絵文字、携帯機種判別、フォームなどの個々の機能を紹介し、モバイル環境でのsymfony開発のアドバイスを行ないます。20100902symfony xop3
http://dl.dropbox.com/u/151520/permalink/20100902symfonyXop3.pdf1.5 「OpenPNEのモバイル機能とsymfony」スピーカー:川原翔吾
【特別LT参加】OpenPNEのモバイルOpenSocial機能について、プラグインの実装者本人のLTです!2. 「OpenPNEコード探訪 - ソースから学ぶsymfony開発テクニック集 -」スピーカー:後藤秀宣
OpenPNE3には、随所にsymfonyを「使いこなす」ためのテクニックがちりばめられています。
このようなソースコードを具体的に取り上げ、symfonyを使った開発実務の現場で役に立つノウハウを紹介します。今回は「symfonyのイベントディスパッチャーを使って将来のカスタマイズに備える」を中心に話します。
OpenPNE同士のID設計【案】
- 2010-09-02 (木)
- 社長BLOG
OpenPNEの設計の話。
複数のOpenPNEをまたいだID設計を考えている。
このID管理体系を発展させ、Twitterや他のSNSサービスにも応用ができるようにしていきたい。
考えたIDは二つ
・ネイティブID
そのSNSに直接所属するID。社員番号や学籍番号みたいに組織が組織のメンバーに発行するIDだと思って欲しい。
・ゲストID
SNSにログインするために利用する外部のID。OpenPNEにGmailのメールアドレスでログインする。というのがこれに当たる。
例を出して、もう少し理解を深めよう。
Twitterの場合は、スクリーンネームがネイティブIDで、参加時に利用するメールアドレスがゲストID。
mixi.jpの場合は、ユーザーID(自分は2936)がネイティブIDで、ログイン用に使うメールアドレスがゲストID。

図示するとこうなる。
OpenPNE同士のサイト連携の場合、@teji.comというSNSのメンバーが@pne.jpというSNSにログインする場合は、mori@teji.com というゲストIDを利用することになる。
mori@teji.comは @pne.jpの運営者の判断でmori@pne.jpというネイティブIDを発行してもらうこともできる。
この辺りが基本構造。
※もう少しまとまったら、改めて記事を更新する。
さくらのVPSにOpenPNE3.6 Betaをセットアップ
- 2010-09-01 (水)
- 社長BLOG
さくらのVPSが正式にサービスインした。
512MBのメモリで月々980円はかなり安い。
さくらには昔から世話になっていたが、クラウドがブームになってからは、少し疎遠になっていた。
今回さくらが本気でサービスを作ってきたのはとっても嬉しい。
※個人的には、クラウドって名前を付けて欲しかったが、
サービスインを記念して、OpenPNE3.6 Betaをインストールしてみたので設置レポートする。
OpenPNE3を快適に動かせる環境かどうか、チェックしてみたい。
さくらのVPSトップ

契約するとこんなコントロールパネルが表示される

リモートコンソールも提供してくれている。ネットワークを間違えて切っても安心だ。

OpenPNE3.6 Betaをセットアップ
できあがりのディレクトリ構造
OpenPNEの本体を設置する場所

Apacheから参照する場所

実体を/home/admin/OpenPNEに設置し、シンボリックリンクを張ってApacheから参照できるようにするところがポイント。このやり方で無くてもいいが、非常にうまく行っているので参考までに。
設置手順
※viエディタがわからない人は nanoエディタを使ってみてください。多少分かりやすいはず。
いきなりOS再インストール

rootのパスワードがわからなかったので、再インストールしてパスワードを設定した。
※【追記】しばらく待っていれば、構築完了のメールが届くようだ。せっかちだったので、メールを待てなかった。
サーバにsshでログイン
OSXであればターミナルから直接ログインができる。

adminユーザーを作成

vi /etc/ssh/sshd_config ssh rootログインできないようにする。

パッケージのインストール
CentOS5そのままではOpenPNE3が必要とするPHP5.2が含まれていない。
Dinoさんのレポジトリを利用し、PHP5.2.11をインストールする。
yum update
rpm -ivh http://nog.dino.co.jp/dist/centos/5/dino/noarch/dino-release-1.0-1.noarch.rpm
yum -y install httpd mysql-server postfix aspell curl gmp libxslt wget httpd-devel php-5.2.11 php-cli-5.2.11 php-devel-5.2.11 php-pear-5.2.11 php-mbstring-5.2.11 php-pdo-5.2.11 php-mysql-5.2.11 php-gd-5.2.11 php-mcrypt-5.2.11 php-xml-5.2.11
yum -y remove sendmail
※単なる install php では libeditがないと怒られ、うまく行かなかった。バージョン指定で乗り切る。
/home/adminのディレクトリパーミッションは755に。

chmod 755 /home/admin
ここ(/home/admin/OpenPNE/xxx.com)にOpenPNEの本体を設置していく。
/var/www/snsにApache側から見たSNSの置き場所を作成

所有者をadminにしているのは、設置のしやすさを考えて。
ダウンロードのリンクアドレスをコピー

ターゲット環境(/home/admin/OpenPNE)でwgetして展開する

お好みでサイト名のディレクトリにリネーム。
今回はIPアドレスにする。普段はドメイン名を指定しているよ。

configディレクトリの中から2つのサンプルファイルをコピー

データベース作成とパスワードを設定

./symfony openpne:install でインストール

おっとメモリが足りない

vi /etc/php.ini で使用メモリを128MBまで増やす

再び ./symfony openpne:install 今度は成功だ

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf でApacheの設定をする

AllowOveride を有効にしておくことがポイント。OpenPNEがmod_rewrite .htaccessで利用する。
シンボリックリンクをはる

実体を設置している/home/admin/OpenPNEとApacheから参照される/var/www/sns/をつなぐ。
設置完了!


APCで高速化【番外編】
このままでもOpenPNE3は動くが、快適に動かすにはAPCを追加で導入するといい。
pearコマンドでAPCをインストール

こんな表示が出ればインストールはOK。

有効にするためには、
/etc/php.ini に extension=apc.so を記述する。
ここでApacheを再起動。
phpinfo()で動作確認。
web/test.php ファイルを作成する。

ブラウザからtest.phpにアクセス。 http://59.106.172.77/test.php

これでAPCの動作確認も完了。
※このサーバは9月7日に解約します。しばらくデフォルト設定のままにしておくので、確認用にどうぞ。
株式会社手嶋屋の社内SNSを紹介
- 2010-09-01 (水)
- 社長BLOG
昨日EGMサミットというイベントに出席させていただいた。
EGM というのはEmployee Generated Media の略で、(主に大企業の)従業員が中心となってつくり上げる、社内ネットメディアのことを指すそうだ。
各社の利用事例を聞いて、刺激を受けた。
今日は手嶋屋も負けてないんだぞと、OpenPNE発明元としての、超絶な使い方を紹介したい。
まずは基本情報から
・メンバー実人数:40人(全スタッフ参加)
・登録種別:社員、業務委託、インターン、卒業生(卒業生はログイン停止)、ボット
・OpenPNEバージョン:3.4.6
・レンタルサーバ:ラックスペースクラウド(RackSpace)512MBメモリ
・OS:CentOS 5.5くらい

これがトップページだ。OpenPNE Ver3.4を利用している。
特徴は以下のとおり。
アクティビティ(つぶやき)

流行りのタイムライン風ユーザーインターフェースを採用した。日記はもう古いね。
全員参加
招待制ではなく、手嶋屋正社員、インターン、業務委託スタッフなど全員が参加している。
全員フレンド
強制的にみんな友達になる。インターンが参加しても、翌日にはみんなと友達になっている。
opAutoFriendPluginを利用して実現。
シングルサインオン
手嶋屋はGoogleAppsでメールやドキュメントの管理をしているが、そのアカウントとOpenPNEをシングルサインオンできるようにしている。
opAuthGoogleAppsPluginを利用して実現。
ランチランダマイザー
ランチのメンバーを自動的に決めてくれるボットプログラムを稼働させている。
opLunchRandmizerPluginを利用して実現。

社内SNSの中で、ランチのメンバー決めだけをひたすら続けてくれるバーチャル社員だ。
世間の声
3カラム目にTwitterのリアルタイム検索結果を表示している。検索文字列は「手嶋屋 OR OpenPNE」うちに対する世間のつぶやきを全メンバーで閲覧できるようにする狙いがある。

GoogleCalendar
GoogleAppsとシングルサインオンしているので、個々のメンバーのカレンダーを表示することもできる。
実験的にだが、OpenPNE内にカレンダーを表示している。
ここで紹介した機能は、すべてオープンソースとして公開している。
http://github.com/tejima
9/24 9/25 PHPカンファレンス2010に参加します。
- 2010-08-31 (火)
- イベント
9/24 9/25 大田区産業プラザPiOにて「PHPカンファレンス2010」が開催されます。
お世話になっているPHPに少しでもお返しができればと、今年はスポンサーとして参加します。

手嶋屋とOpenPNEプロジェクトはブース出展、セミナーでの講演を予定しています。
セミナーでは、最新バージョンであるOpenPNE3.6の新機能を中心に、今後のロードマップなどを発表する予定です。
※詳細が決まり次第続報をお届けします。今のうちから予定を空けておいてください。
とっさの即席カーテン
- 2010-08-30 (月)
- 社長BLOG
引越しをした最初の夜、この部屋にカーテンが無いことに気づいた。
そんな経験はないだろうか?
さて困ったどうしよう、という時のライフハック。
用意するもの
・IKEAのセールで買った掛け布団カバー。中の布団は出した。

・普通のホッチキス。

この二つがあれば、即席カーテンが出来上がる。
即席カーテンの作り方
作り方は簡単。まず布団カバーの一辺に等間隔でホッチキスでパンチを打っていく。
カーテンレールのコマの数だけ打つ、今回は15ヵ所にパンチ。
ホッチキスの工夫が今回のポイントだ。
針の片側だけがカバーにかかるようにパンチする。もう片側はわざと空振りさせておくのだ。
そして空振りした方の針を開いて、フック状の形にする。
あとはそれをカーテンレールに引っ掛けるだけ!

なんとこれだけで、立派なカーテンができあがる。

ほら、どう見ても普通のカーテンにしか見えない。
なんだかもう、このままでもいいんじゃないか?という気がしてくるぐらい、部屋に馴染んでいる。