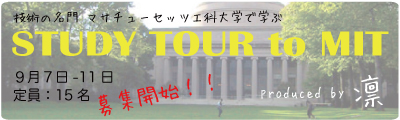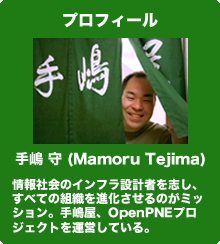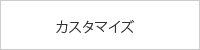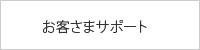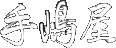社長BLOG
OSS化のススメ
- 2010-08-23 (月)
- 社長BLOG
自社製品のオープンソース化を検討する企業に対するアドバイス。
OSS関連の書籍から学ぶ
・伽藍とバザール
http://cruel.org/freeware/cathedral.html
・JustForFun
・The Apache Way
OSSの先輩プロジェクトから学ぶ
・WordPress
http://wordpress.org
・OpenPNE
http://www.openpne.jp
経験から学ぶ
とにかくいち早く公開し、利用者のフィードバックに耳を傾ける。これが一番大事。
ソースコードが未完成でも、美しくなくてもいいので、公開する。
プロジェクトの運営も、相談もすべて公開された場所で行うことが必要だ。
ライセンスは頭を悩ますところだが、とりあえずソースを公開したうえで
「全著作権は◯◯に帰属します」としておけばOKである。
その後ライセンスを設定しても問題はない。
ちなみにOpenPNEプロジェクトの経験についてセミナーで話したものがある。
https://www.tejimaya.com/archives/5804
オープンソースの先輩、wordpress.comのUUがすごい
- 2010-08-20 (金)
- 社長BLOG
http://www.google.com/adplanner/static/top1000/
より、オープンソースのプログエンジンWordPressの商用ホスティングサイト、wordpress.comのユニークユーザー(UU)がすごい。

TwiterやBingを押さえてTop12位に位置している。
1億2000万ユニークユーザーというとてつもない数だ。
※Facebookのページビューも2位と十倍近くの差をつけ、ダントツですごいんだけどね。
理系女子大生コミュニティ「凛」がMITへのツアー参加者を募集中
- 2010-08-19 (木)
- 社長BLOG
理系女子大生コミュニティの「凛」がマサチューセッツ工科大学(MIT)へのスタディーツアーの参加者を募集している。
「凛」代表の辻さんには、Jobwebのインタビューの時にお世話になった。
http://student.jobweb.jp/contents/engineer/6302
その時以来、仲良くさせていただいている。今回、その「凛」がMITへのスタディーツアーを行うとのこと。
自分も19歳の時、MITに見学に行ったことがある。その時は単なる観光だったので、今回のようにスタディツアーとして中の人たちと交流することはできなかった。
自分が学生の時にこうしたプログラムがあったら、絶対に参加していただろう。
しかも今回は、理系女子サークルの企画だ。当然女子の参加が多そうだ!
ボストンにはハーバードもあるし(キャンパスにリスがいる)、湖や森はとてもステキだ。
ぜひサイトで詳細をチェックし、申し込んで欲しい。
http://rikeigirlsrin.blog103.fc2.com/blog-entry-247.html
===================================
HOW DO YOU BECOME A SPECIALIST?
———————————–
米・MITで学ぶ
スペシャリストとしてキャリア形成を
考えるスタディーツアー
・ ・ ・ ・ ・ ・
一 般 参 加 者 募 集 開 始!
===================================
「変化が激しい世の中だからこそ、
自分の強み を持たなければならない」
自分で自分のキャリアを築く必要性が
説かれるようになっている。
では、具体的に何をするべきなのか?
それをイノベーションの最先端を走って
いる人たちにきき、スペシャリストとして
キャリアを築く上で必要な観点を知る。
これが本スタディーツアーの目的です。
今回この目的に共感し、
インタビューやディスカッションに参加する
一般参加者を募集いたします!
また、事前インタビューとして、
MITメディアラボ副所長・Tangible Bits研究創始者の、
石井裕教授へのインタビューを東京にて実施いたします!
(8/15までにご応募いただいた方のみ同行可)
石井教授HPはこちらです。
一生に一度のチャンスです。
この機会をお見逃しなく!
===================================
ツアー概要
===================================
【実施期間】
9月7日~9月11日
※9月7日 MITにて現地集合
※9月11日 ボストン市内にて解散
※9月5日 東京にて石井裕教授に事前取材
(一次募集応募者のみ同行可・参加任意)
(時間・場所等詳細は追って連絡いたします)
【プログラム内容(仮)】
9月7日
MITキャンパスツアー
大学職員インタビュー
9月8-9日
現地スペシャリストインタビュー
※詳細調整中
エンジニア、研究者等に依頼中
9月10日
現地大学生インタビュー
ツアー参加者によるディスカッション
【参加費】
プログラム参加費 5万円
(※渡航費、宿泊費等は含まれません)
【参加資格者】
・将来スペシャリストとしてのキャリアを築いていきたい方
・海外に留学したいと思っている方
・海外でのキャリア形成の実態を知りたい方
※社会人・学生・性別は問いません
9/2 OpenPNE3で学ぶsymfony勉強会@Nifty(19:00〜)
※告知をATNDに集中させます。
【お申し込み方法】
参加をご希望の方は、ATNDからお申込みください。
http://atnd.org/events/7417
【お問い合わせ】
twitter @tejima にご質問ください。
http://twitter.com/tejima
勉強会用に会場を提供してくれる企業のまとめ【更新中】
- 2010-08-16 (月)
- 社長BLOG
OpenPNEの勉強会用に会議室を提供してくれる企業のまとめ。
※あくまでもOpenPNEの勉強会でOKしてもらっただけなので、自分のイベントが利用できるかどうかは、それぞれ確認してください。
Nifty
@nifty エンジニアサポート
http://twitter.com/nifty_engineer
http://www.rbbtoday.com/article/2010/08/11/69814.html
http://www.nifty.co.jp/release/2010/pdf/nifty20100811_1300.pdf
所在地:東京都品川区南大井6-26-1 大森ベルポートA館
IDCフロンティア
カスタマーソリューションセンター

http://bit.ly/a6dBlv
http://www.idcf.jp/topics/20100428001.html
所在地:東京都新宿区四谷4-29
「弊社お客様や技術者の方々を対象といたしましてご支援させて頂ければと思います」
http://twitter.com/tadaakiban
さくらインターネット
※調整中
今のところすべてISP、IDC、レンタルサーバとネットインフラの会社というのがおもしろい。
※OpenPNEプロジェクトでは、勉強会開催のために会場を提供してくださる企業や団体を募集します。OpenPNEプロジェクトから生まれたすべての成果は、オープンソースとして公開されます。プロジェクト発展のためにぜひご協力下さい。
iPadはノートパソコンの代わりにならなかった
- 2010-08-16 (月)
- 社長BLOG
iPadを使って外出してみたが、ノートパソコンの代わりには残念ながらならなかった。
今はiPhoneとMackBook PROを持ち歩いている。
以前のレッツノート時代よりも重量が1Kgほど増してしまった。
・キーボードが打ちづらい(Dvorak配列じゃない、キーストロークが無いので押し間違えがおおい)
・無線の到着が遅れた。PocketWifi的なやつ
・セミナー等ではパワーポイントをプロジェクタに繋げる必要がある。その場合はやはりパソコンが必要。
・自作のアプリが動かない
この辺りがダメージだったと思う。
iPadは実家にプレゼントし、シニア向けデバイスとして現在活躍中だ。
シェアハウスとOpenPNE
- 2010-08-12 (木)
- 社長BLOG
シェアハウスをご存知だろうか?最近出てきた概念なので、明確に固まった定義は無いようだが
・ゲストハウスの定住版
・社員寮形式だけど、入居者はバラバラの一般人
とイメージしていただければ分かりやすいだろうか?
要するに
「自分の部屋は狭い代わりにリビングやキッチンなどの共有設備が充実している賃貸住宅」
ということだ。弊社のクライアントではグローバルエージェンツ社がソーシャルアパートメントを展開されている。

写真は恵比寿の物件だが、このとおりリビングがめちゃくちゃ広い。
さて、こうした共同生活とOpenPNEの接点はなんであろうか?
共同生活と言うことは、
ひとつ屋根に住む、居住者コミュニティ
という、新しいコミュ二ニティ=組織が生まれるのだ。
賃貸に「コミュニティ」という新たな要素が加わった。
この組織をうまく運営し、維持発展することが、物件を管理する不動産会社の新たな課題となる。
これまでは、1DK、駅前徒歩5分、バストイレ別、オートロック付きなどの物件スペックが、商品の価値を決めていた。
今後は、
コミュニティ状況良好、OpenPNE完備
と物件情報に追加されるようになる。
居住者コミュニティでも利用できるように、OpenPNEを進化させていきたい。
OpenPNEで目指すドラッカー越え
- 2010-08-12 (木)
- 社長BLOG
多くの経営者に愛されているドラッカー。
※最近は女子高生にも人気みたいだけど
ドラッカーを読んで実践しようとした経営者共通の悩みがある。
それは、
スタッフがドラッカーを読んでいないこと
これに尽きる。
本に書いてあることは、会社だけでなくどんな組織にでも当てはまる本質ばかりだ。
これは時代を超え、いつでも古くならないので、本としては素晴らしいのだが、どうしても内容が抽象的になってしまう。自分の組織に当てはめるためには、結構なイマジネーションが必要になる。
「ドラッカーの教えを元にスタッフが考え、行動してくれたら、この組織はよくなるのに、、」
なんて思っても始まらない。ドラッカーを読んで真面目に働くような人であれば、経営者をやっているか、さっさとフリーランスでもやっているはずだ。
結局経営者ばっかりが本を読んで頭でっかちになって、スタッフは
「なんだか社長は小難しいこと話しているなぁ」
という状況になるのだ。
すなわち、
ドラッカーの本だけでは、組織を進化させることができないのだ!
※言っちゃった、ドラッカーファンごめんなさい
自分は、組織そのものを表現するOpenPNEにドラッカーの教えを埋め込むことで、ドラッカーの本では実現できない組織の進化を、達成したいと考えている。
一般従業員がドラッカーを読むことはないけど、一般従業員がドラッカー風味のOpenPNEを毎日使うことはあり得る。ということ。これがドラッカーを越えるチャンスなのだ。
※ほうれん草が練りこまれているパスタを食べれば、ほうれん草をわざわざ食べなくても、簡単に野菜の鉄分とビタミンが補給できるという感じかな。ほうれん草が嫌いなお子さまでも食べられる!的なね!
本は読まないけどOpenPNEは使う。OpenPNEにドラッカーを混ぜておけば、無理なくエッセンスを吸収することができるのだ。
本はどこまで行っても紙や情報だけど、OpenPNEは組織や社会そのもの。組織を進化させるなら、組織そのものにアプローチすればいい。
組織を進化させるソフトウエアである、OpenPNEをつくりだす能力が自分にあることが、とても幸せだ。
情報社会はOpenPNE、分散型で設計する
- 2010-08-12 (木)
- 社長BLOG
mixiが丸24時間を超えるサービス停止を起こした。
自分はSFで描かれているような情報社会は、現在のmixi、GREE、Facebook、Twitter、そしてOpenPNEといったSNSが発展してできていくと確信している。
今回の一件で考えたのは、今後の情報社会は、マス型中央集約的なソーシャルネットを基盤とすべきか?それともOpenPNEを中心とした、分散型のソーシャルネットを基盤とするか?どちらの設計がより適しているか?ということ。
自分は後者、分散型が最適であるとこれまた確信している。
※そもそも分散型の情報社会を作りたいから、OpenPNEをつくりはじめたわけなのでね
現在のSNSでは、実際に使われているのは、飲み会の調整やサークルの連絡、そしてみんなでゲームという娯楽レベルだ。今回のサービス停止が起きても、個々のユーザーにとってのダメージは、せいぜい楽しみがひとつ減りましたというぐらいだろう。
しかし今後、社会の重要な役割をどんどんSNSの中に取り込んでいくとそうは行かない。生活、仕事、娯楽と社会的なコミュニケーションすべてがひとつのサービス停止で一気に不通になってしまうのだ。
それなら、こうした情報社会の基盤ははじめから分散型の設計にしておいて、会社、学校、趣味、地域、家族とそれぞれがソーシャルネットを持っているのが望ましい。たとえ会社が潰れても地域で、地域がダメでも家族で、と多重化されたフェイルセーフ的デザインが望ましい。
ちょうどインターネット自体が障害への耐性を高めるために、複数の情報経路を取れるように。
マス型SNSには、いつ止まってもいいマス型エンタメソーシャルネットを任せておこう。情報社会の重要な基盤は、OpenPNEをベースにして分散型で作っていこう。
※今度リリースするOpenPNE3.6はさらに情報社会の基盤として、充実してきているよ。