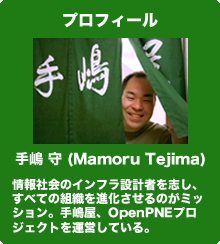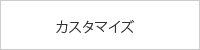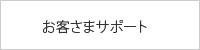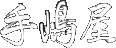社長BLOG
OpenIDはパスポート仕様と同じ、それだけで入国できるわけではない
- 2010-06-09 (水)
- 社長BLOG
技術は正しく理解して社会に役立てようというのが、エンジニア社長としての自分のスタンス。
最近のOpenIDについての話題も気になるところがある。
OpenIDは現実世界に例えるなら、国際パスポートの仕様と同じ。
パスポートを持っている所有者を信用できるわけじゃなくて、国ごとにビザを発行したり、指名手配犯を除外したりしている。
OpenIDはパスポートみたいなものだから、ビザの発給や、国交を結ぶ国を選ぶのは別の仕組みを考えようね。
と、的確に話しを進めていってもらいたい。
※ちなみにOpenPNE3はOpenIDの発行側も利用側も対応しているよ。
オープンソースを広めたい
- 2010-06-09 (水)
- 社長BLOG
2005年にOpenPNEをオープンソースソフトエアとしてリリースしたときから、自分のミッションを実現するための本格的なステップを踏み出すことができた。
今思うと、大学時代、もっと言えば無限に時間があった、中学生の時にオープンソースに出会っていたらもっと良かったと思う。
オープンソースプロジェクトに関わる楽しさをもっと啓蒙していきたい。
そのためのイベントを考えるよ。
GoogleAppsとOpenPNEをつなぐプラグインを作成
- 2010-06-06 (日)
- 社長BLOG

GoogleAppsにOpenPNEをぶら下げる(シングルサインオンする)プラグインを作成した。


とりあえずこんな感じにしておけば、ログインOK。
バージョンはまだ0.5 ベータ版だが、会社組織にOpenPNEをまるごと導入するにはなかなか良い作戦だと思うんだ。
プラグインのページはこちら。
http://plugins.openpne.jp/release/196
OpenPNE3がセットアップ済みなら
./symfony opPlugin:install opAuthGoogleAppsPlugin -r 0.5 -s beta
これでOK(マイグレートは必要ない)。
エンドユーザー向けサービスは、内製しないと間に合わない時代に
- 2010-06-03 (木)
- 社長BLOG
リアルタイム&ソーシャルの時代のキーワードは
・エンドユーザーとの対話
・エンドユーザーの期待に答えるスピード
この二つに尽きる。
そうなると、従来のようにWEBシステムを外注して要件定義、開発、テスト。なんてやっていては本質的に間に合わない状況が起きる。
今後エンドユーザーが直接触れるサービス部分は、サービス事業者が技術者を雇用して、内製をするしかなくなってくるだろう。
TwitterもFacebookもmixiもGREEもモバゲーも基本的なコミュニケーション部分はすべて内製している。
ソーシャルコミュニケーション自体を本業としているこれらの会社が内製するのは当たり前として、そうでない企業はどうしたらよいか?
例えば、飲食店チェーンを経営して、顧客とのコミュニケーションにソーシャルネットワークを構築したいという会社。アーティストとファンの関係を良くしたい、事務所。年間100万円以上売り上げるVIP顧客に対して、顧客クラブを形成したいブランド。
こうした会社も、結論としては開発者を抱えて内製する必要がある。
ただ全部を作る必要は無い。そこで登場するのがOpenPNEだ。エンドユーザーと接する部分、すなわちアプリケーションはプラグインやオープンソーシャルで作る。そのベースエンジンとしてOpenPNEを利用してもらいたい。
OpenPNEはあらゆる組織のコミュニケーション基盤になるように設計している。
OpenPNEはエンターテインメントから大企業まで、どちらに偏ることも無く、組織コミュニケーションの本質を追求している唯一のソフトウエアだ。
OpenPNEグッズを売りたい
- 2010-06-02 (水)
- 社長BLOG
OpenPNEプロジェクトでやり足りないこと。
これだけ広まったOpenPNE。Tシャツやステッカー、マウスパッドなどのグッズを作って販売したいな。
どうもhttp://www.zazzle.com/ というサイトでできるみたいだ。
とにかく開発で忙しいOpenPNEプロジェクトだが、こんなところからもプロジェクトを盛り上げていけたらいいな。
「組織をWeb上に表現する」とはどういう事か?
- 2010-06-02 (水)
- 社長BLOG
OpenPNE上であらゆる組織が活動できるようにすることが、OpenPNEのミッションであり、そのために、現在ある組織をWeb上で表現できるように開発を進めている。
それって何だ?話している自分でもよくわからない。少し噛み砕いてみたい。
組織の中でも分かりやすく会社組織を例において
「既存業務Webシステム」と「OpenPNE 組織表現システム」
との対比をしてみよう。
既存の業務Webシステムは、業務をWeb上に表現する試みだ。
電子メールは社内社外の関係者との連絡業務を
グループウエアは日程の調整や、ワークフローなどの業務を
通信販売は、商品の選択、注文、支払いなどを業務を
それぞれ表現している。
これらは業務をこなすことはできるけれど、それを使う人や組織を正しく表現できてはいない。努力はしているみたいだけど、ソーシャルの専門家から見たらかなり甘い。というか破綻している。無理だ。
※業務システムの人たちから見たら、OpenPNEに付いている業務システムの出来についても文句があるとおもうけどね。
一方でOpenPNEは業務ではなく組織自体の表現を目的に作られたソフトウエアだ。
会社組織というのは業務だけでできているわけではない。実際にはもっと複雑だ。
会社の夢や使命を元にした連帯、同期の仲間、サークル活動、社内恋愛、福利厚生、組合、地域社会とのつながりなど、多くの人間関係、組織関係を組み合わせて出来ているのだ。
こうした業務を超えた、組織全体の人間関係を表現するのが、OpenPNEの役割じゃないかと思う。
結論としては、OpenPNEで会社組織を表現し、その組織の上で個々の業務システムを連携させていくのが、ベストな組み合わせではないかと思っている。
OpenPNE上でOpenSocialかプラグインを使って、業務システムを構築すればいいのだ。
まとめ
・業務をこなすのか?組織を表現するのか?は別々の概念だ
・業務システムは組織を表現できていない
・OpenPNEは組織を表現することを目的に作られている
・業務システムはOpenPNE上に構築するのがベストだ
OpenSNPもオープンごろっともOpenPNE3ベースにしたほうが良いと思う
- 2010-06-02 (水)
- 社長BLOG
これを書くと物議をかもすかもしれないが、本音なので。
地域SNSを構築するためのSNSエンジンは、自分が知る限りOpenSNPとオープンごろっと、OpenPNEがある。
OpenPNEプロジェクトは、この世のすべての組織のためのコミュニケーション環境を提供すること、ようは「ネットワーク社会をつくること」を目的にしている。
現在500以上あるSNSのうち数量ベースで70%程度がOpenPNEかOpenPNEを拡張したソフトウエアで運用されているようだ。
OpenPNEは企業やゲームコミュニティ、ファンクラブなど、100万人規模のスケーラビリティと、多様な組織を表現するための多様性を備え進化している。
地域SNSという限定されたニーズで、ソフトウエアが3本もあるのはエンドユーザー、地域SNSの運営者やその先の利用者にとってメリットがあることなんだろうか?地域の課題を解決するために、ソーシャルコミュニケーションが役立つと思うから、それぞれソフトウエアを開発しているんだと思う。それなら、3つのプロジェクトが協力して開発をしたほうが、もっと地域社会のためになるんじゃないだろうか?
OpenSNPプロジェクトにも、オープンごろっとのプロジェクトにも、ぜひともOpenPNE3のプラグインを開発し、地域SNSの機能を実現していただきたい。
一番しんどくて目立たない組織表現のインフラは、OpenPNEが担うから。
【つぶやき】iPadのGoogleMapを見ていると、世界が小さくなった気がする。
- 2010-06-01 (火)
- 未分類
よーし南房総ドライブ行っちゃうぞ。なんて気持ちになる。弾丸ハワイツアーじゃ!とかね。
(pne.jpから)