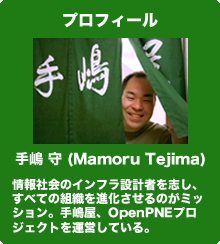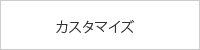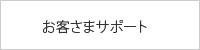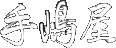社長BLOG
手嶋屋トライアル#3@新宿御苑 5/22から開催
- 2010-05-11 (火)
- 社長BLOG
「世界に広がるOpenPNE、共に創る仲間を募集」
手嶋屋では、ともにOpenPNEの開発に参加してくれる仲間を必要としています。
この選考会に参加し、通過することで、有給でOpenPNEの開発に参加することができます。
・オープンソース開発を職業にしたい
・世界に広がるソフトウエアの開発に参加し、実力を磨きたい
・自分の生み出したソフトエアで世界を変えたい
こんな意欲を持った方の参加をお待ちしています。
定員 / 10 人
会場 / 手嶋屋新宿御苑オフィス(新宿鈴木ビルA館 7F) (東京都新宿区新宿1-6-8)
URL / URL :http://tejimaya.com/tag/trial
参加条件:
・高校生以上であること
・SSH接続可能な無線LAN付きノートパソコンを持参できること
・2回のトライアル選考会に両方とも参加できること
・トライアルの課題(宿題)に取り組めること
参加申し込みはATNDから。平日コースと休日コースの2コースに分かれています。
【掲載開始】株式会社手嶋屋 – 自社開発オープンソースのWebプログラマの転職・求人情報
- 2010-05-07 (金)
- 社長BLOG
電子出版の短期、長期戦略
- 2010-04-25 (日)
- 社長BLOG
短期:所有感(マテリアル感)の演出による課金
ユーザーはモノの所有に対しては、今のところかなりのお金を払う。
PC上のカレンダーはお金払わないけど、紙の壁掛けカレンダーにはお金を払う。
ネットに転がっているグラビア画像にはお金を払わないけど、iPhoneの写真集にはお金を払う。
DVDBOXにもお金を払うし。話した例がデジタルアナログ混在だけど、所有したい感覚、手元に置きたい感覚は共通していると思う。
電子書籍でもこの感覚を感覚を演出することが、短期的にはよさそうだ。
長期:ソーシャル化による会員ビジネス
今後出版物は、情報を提供する「情報キャリア」という側面と、特定の人を引きつける「旗や柱」としての側面の二つの要素で展開していくようになる。柱というのは表現しにくいが、この指とーまれの指だと思うと分かりやすいかもしれない。
長期的には既存メディア側がどう思っても、価格低下圧力は強まる。
無料か、課金してもものすごく安い単価でしか儲けられなくなる。
なぜなら、制作や流通にかかるコストがどんどん下がって、代替手段がバンバン出てきて、比較優位がなくなってくるから。
ただ、現在でも無料で発行出来ている媒体は少なくない。
ファンクラブ会報誌が無料なのは、ファンクラブの会費か、CDやイベントの売上があるからだし、クレジットカードに付いてくる会報誌も、カード本業の売上で発行されている。
ソーシャルメディア時代では、情報よりも「人と組織、そのつながり」が重視される。
「短期的にはマテリアル感を演出したサービスを展開し、来るべきソーシャル時代に備えた模索を開始する。自らの価値を毀損する自爆にだけは注意して。」
登紀子さん朝日新聞でTwitter、iPhoneを語る。
- 2010-04-24 (土)
- 社長BLOG
23日付けの朝日新聞夕刊(一部24日朝刊)で、登紀子さんがiPhoneからTwitterを活用しているというインタビューが掲載された。
※iPhoneを教えたのも、Twitterを教えたのも自分だよ!
現在18,696人のフォロワーがいて、月に500件程度投稿やリツイート(RT)をしている。ものすごい活躍だ。
実家にもこの記事を送っておいた。登紀子さんと同い年の親が、これでインターネットに目覚めてくれればよいのだが。
この記事は、アサヒ・コムにも掲載されている。
アイフォーンで、ツイッターを使う練習を始めてみると、「またたく間に、はまりましたね」。今では友人が驚くぐらい速く打ち込む。
引用元: asahi.com(朝日新聞社):〈メディア激変20〉この人が使う―1 新しい言葉を呼んでくる – メディア激変.
加藤登紀子さんの「君が生まれたあの日」を聴いて
- 2010-04-23 (金)
- 社長BLOG
縁があり、加藤登紀子さんのSNSやソーシャルメディアを使ったプロモーションをお手伝いさせていただいている。
iTunesからのシングル、iTunes限定アルバムと登紀子さん初の、ネット中心リリースとなった。
アーティストが直接ファンに届ける。そのために道具してテクノロジーを使う。
この手伝いができるのは技術者冥利につきる。
この曲の編曲者は菅野よう子さん。
菅野よう子といえば、攻殻機動隊や創聖のアクエリオンといったスケールの大きいSF作品というイメージがあった。
アニメやSF以外の曲も手がけるんだーというのが最初の驚き。そうやって調べてみると、紅の豚のテーマ「時には昔の話を」も手がけていたのだ。なんとまあ。
アレンジはやはり壮大で、ストリングス、ピアノを中心に楽器もたくさん使っている。
これに登紀子さんの声がばちんと張り合っている。父親の思いを歌った曲なので力強い。
※登紀子さん自信はとても可愛らしい人なんだけれど。
曲を聴いてみた印象だが、この曲からは、子供の成長を優しく、強く見守る父親のイメージが伝わってきた。
自分の父親は6歳の時に亡くなっているので、直接聞くことはできないが、
もし父親が生きていたら、こんなことを考えてくれたのだろうか?それは本当にありがたいな、と素直に感じた。
「君が生まれたあの日」が含まれている、iTunesオリジナルアルバムは、非常に好調とのこと。よかった!
記念に、iTunes小窓も作成した。ぜひ視聴していただきたい。
なぜソフトウエアエンジニアが人材難になるのか?
- 2010-04-20 (火)
- 社長BLOG
シリコンバレーでソフトウエアエンジニアが不足している。
世界で活躍していく時代に必要なのは、素晴らしい感性とセンスを備えたプログラマであるのだ。
状況は引用元のブログを参照していただきたい。
昨今引く手あまた感が強いのはやはり「今・ここで、気の利いたコードがバリバリかけるソフトウェアエンジニア」。
最先端のウェブサービス開発の現場は、とてもアウトソースなんかできない状況になっている。「仕様書を文章で作って、それを誰かが作る」なんていう悠長なやり方は通用しない。どんどん機能開発して、どんどんリリースして、ユーザーのフィードバックを元にさらに進化させる、というのを、毎日行い続けないとならない。
引用元: On Off and Beyond: ITアントレプレナーになりたい若者のみなさんはプログラミングを習得しましょう.
さて、大局的にみて、今なぜソフトウエアエンジニアが必要とされるのか?を説明しよう。
社会のネットワーク化、バーチャル化が進行すると、生活や仕事、娯楽も徐々にネットワーク上で行われるようになる。そこでは人が仕事をするのと、人によって作られたソフトウエアが仕事をするのは等価であり、一般的にプログラムのほうが安く、よく働くようになる。
合理的に考えれば、なるべく多くのものを自動化し、ソフトウエアプログラムに置き換えようという力が働く。
こうして既存の仕事は、ソフトウエアに追い立てられるようになり、追い立てるソフトウエアを生み出すことのできるエンジニアは重宝されるのだ。
もちろん、アーティストのライブ生演奏は、バーチャルに置き換えることはできないし、レストランで気持ちの良いコミュニケーションをしながら食事をすることも、バーチャルには無理だ。でも、喜びや感情、生身のコミュニケーションを必要としない仕事は山のようにあるし、これらはソフトウエアに置き換えられたほうがいいと思う。
※ソフトウエアエンジニアの将来は明るい。この能力を身につけたかったら、ぜひOpenPNEプロジェクトか手嶋屋へ!
ACCESS がスマートメータでスマートグリッド市場に参入 – japan.internet.com Webテクノロジ
- 2010-04-20 (火)
- 社長BLOG
これは面白い。
ACCESSは自分が学生時代から大変お世話になった会社だ。
業界人にしかあまり知られていないが、この会社は日本で数少ないソフトウエアの輸出企業だ。
携帯用組み込みブラウザで海外でも30%近くのシェアを持っている。(おそらく現在でも?)最近スマートフォンブームが来ているせいで、組み込みブラウザのACCESSはどうだろうか?と思っていたところだ。
もっと深くもっと小さなところに潜るんだな。たいしたもんだ。
自分ももっと精進せねば。
携帯端末や情報家電向けブラウザメーカーのACCESS は2010年4月20日、スマートグリッド(次世代送電網)市場に参入することを発表した。
引用元: ACCESS がスマートメータを開発、スマートグリッド市場に参入 – japan.internet.com Webテクノロジー.
Felicaのイノベーションは何か?問題点は何か?
- 2010-04-19 (月)
- 社長BLOG
SUICAやEdyなどの電子マネー、iDなどのクレジットで利用されている基盤技術をFelicaという。これはSONYが開発した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/FeliCa
個人的にFelicaはここ10年では一番すごい技術だと思う。
革新的なのは、その再利用性。従来の磁気カードに比べ、原理的にはほぼ無限に再利用ができる。
自分は9年前SUICAのスタート時に記念に学生定期を作ったのだが、そのが今でも使えるのだ。これはすごい。エコだしね。
ただ問題もある。それは革新的過ぎたところ。
・再利用が可能なので磁気カードを発行しなくてもよくなる
・非接触なので、従来のようなメカ部品がなくなり、故障が少なくなる
この二つは、発明者であるSONY自体を苦しめることになる。
簡単にいうと、
「国民全員にカードを発行したらビジネスが止まる」
ということ。複数枚配ってもせいぜい10億枚もあれば十分だろう。読み取り側もなにせ壊れないものだから、一度配置したらそれで終わり。掃除などのメンテナンスも、メカ部品が無いから簡単。駅員さんが仕事のついでにキュキュっと磨いておけばいい。
これじゃあまずいということで、Edyビジネスをはじめてみたのだが、うまくいかず、そのEdyは今や楽天の傘下にある。
うーむ。もったいない。
以前にも、こんなブログを書いた。
もし自分が日本のCTOだったら?電子マネーを日本円にする。
一方で今、国民IDを発行しようという議論が上がっているそうだ。
自分が日本のCTOなら、上限3万円でFelica仕様の国民ID付きお財布カードを配り、日本から小銭をなくすね。
人々を幸せにする最高に優れた技術を生み出したのであれば、政府が買いあげてあげればいいと思う。
新幹線やトンネル技術、原発のように、国家電子マネーシステムを作り上げ、海外に輸出できるようにしよう。そうすれば儲かりそうじゃない?
【つぶやき】ガラパゴスケータイの開放は遅すぎた。
- 2010-04-19 (月)
- 社長BLOG
今から開放するのは難しい。戦略的な準備が必要だった。その準備とは一言で言えばフェリカ機能の取り外しだ。SDカードなどで取り外し可能にしておけばよかった。自分がそのポジションにいないのが悔しく、残念でならない。
(pne.jpから)
日経新聞社主催の公開セミナー@大手町(4/23 18:30~20:00)に参加

4/23 18:30~20:00 大手町KDDIホールで開催される
日経新聞社主催のオープンセミナー
「技術者が語る、テクノロジーと新時代のメディア」
に参加する。参加は無料(事前登録制)だ。
参加者は手嶋の他に、
伊藤 正裕氏(ヤッパ社長)
猪子 寿之氏(チームラボ社長)
金 正勲氏(慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科准教授)
楠 正憲氏(マイクロソフト 法務・政策企画統括本部 技術標準部部長)
赤沢 大典(日本経済新聞社 デジタル編成局事業企画部次長)
と豪華な顔ぶれ。
自分は技術ベンチャー企業側として参加させていただく。
慶応、マイクロソフトからは政策に関わる部門が参加。
最近のネット選挙解禁やオープンガバメントの話題も語られることになるのではないか?
自分のポジションとしては、いつもどおり
「組織を進化させるため、あらゆる組織にOpenPNEを提供する」
を基本として、朝日新聞や佐賀新聞との取り組みで感じたことを話したい。
オープンガバメントやネット選挙解禁となれば、519以上ある地域SNSの活用事例や、問題点などの話を展開したい。
詳細は日経新聞社側のページを確認していただきたい。
(リンク切れのためリンク削除)
記事の最後にメールで届いた案内を添付する。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
オープンフォーラム
「技術者が語る、テクノロジーと新時代のメディア」
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆【開催概要】
日 時 : 4月23日(金) 18:30~20:00
会 場 : KDDIホール
東京都千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル2階
http://www.kddihall.co.jp/map.html主 催 : 日本経済新聞社
協 力 : 日経デジタルコア
中継協力: 杉並TV(http://www.suginami-tv.jp)
定 員 : 50名
参加費 : 無料(事前登録制)
申込締切: 定員に達した時点で締め切りとさせていただきます。
パネリスト:
伊藤 正裕氏(ヤッパ社長)
猪子 寿之氏(チームラボ社長)
手嶋 守氏(手嶋屋社長)
金 正勲氏(慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科准教授)
楠 正憲氏(マイクロソフト 法務・政策企画統括本部 技術標準部部長)
赤沢 大典(日本経済新聞社 デジタル編成局事業企画部次長)司 会:日本経済新聞社 デジタル編成局編成部 重森 泰平
*ネット中継の実施を予定しています。
詳細は当日、下記ウェブサイトにてご確認ください。
(リンク切れのためリンク削除)
(リンク切れのためリンク削除)===============================
◆ご参加希望の方は、下記に必要事項ご記入の上メールでお申し込み
ください。◆参加証はメールにてお送りいたします。
◆定員を超えるお申し込みがあった場合は、先着順で参加証をお送り
いたします。ご了承ください。————オープンフォーラム申込票————————
digitalcore@nex.nikkei.co.jp までお送りください。4/23 オープンフォーラムに参加します。
御所属(会社名・部署名など):
御名前:
メールアドレス:
本フォーラムへの参加にあたりご登録いただいた個人情報は、参加に伴う
一連の手続き(確認メールなどの送付、当日の受付作業など)に利用する
ほか、日本経済新聞社が行うイベントについての情報をお送りするために
利用させていただきます。今後イベント情報を希望しない場合、下記の( )に×をご記入ください。
イベント情報の送付→( )——オープンフォーラム申込票ここまで———————
お問い合わせ等につきましても上記メールアドレスにて承ります。
皆様のご参加を心よりお待ちいたします。